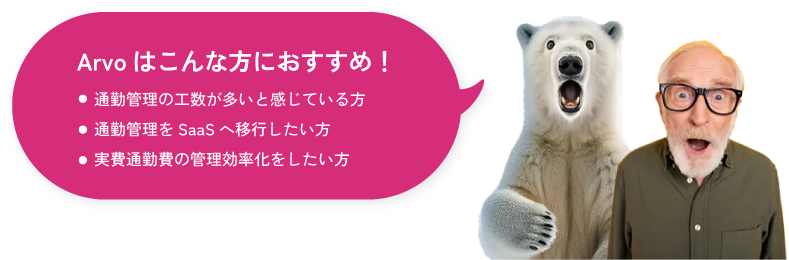通勤手当と距離の関係|通勤手段による違いも解説
通勤手当の支給には、通勤手当と距離の関係が深く関わっています。 通勤時の距離は、通勤方法を決定する際の重要な基準となるためです。
通勤手当と距離の関係について、解説していきます。
Arvoで通勤管理を
今すぐ効率化
通勤手当の概要
通勤手当は多くの企業が福利厚生として導入しており、支給の有無、金額、条件は各企業の就業規則で定められます。 交通費と混同されがちですが、通勤手当と交通費はその性質上、明確に区別されます。
通勤手当の基本的な定義
通勤手当とは、従業員が自宅から会社までの通勤にかかる交通費を補助する目的で、会社が従業員に支給する手当です。
これは労働基準法で支給が義務付けられているものではなく、企業が任意で定める福利厚生の一環として位置付けられます。
義務ではありませんが、多くの企業が通勤手当を導入しており、厚生労働省の調査によれば、従業員30人以上の会社の92.3%で支給されている状況だそうです。
通勤手当支給の有無や額、支給条件などは、各企業の就業規則や労働契約によって自由に定められます。
交通費と混同されがちですが、通勤手当は「通勤にかかる費用」を指し、交通費は「業務上の移動にかかる費用」を指す点で明確に区別されます。
また、通勤手当は給与所得の一部として扱われますが、一定の非課税限度額が設けられており、その範囲内であれば所得税が課税されません。
ただし、社会保険料の計算においては、通勤手当も報酬として含まれるため、社会保険料が増える可能性があります。
通勤手当の算出基準
通勤手当の支給基準は、従業員の通勤手段や距離に応じて多岐にわたります。
特に、マイカー通勤や自転車通勤の場合には、距離に応じた支給額が設定されることが多いでしょう。
基準を適切に設定することで、従業員への公平性を保ちつつ、企業の費用負担も考慮した運用が可能となります。
会社が定める支給要件
通勤手当の支給要件は、会社が就業規則や賃金規程によって自由に定めることができます。
労働基準法には通勤手当に関する明確な規定がないため、支給の有無、支給対象となる通勤手段、支給対象となる最低通勤距離、支給金額の上限などを会社が独自に決定することになります。
例えば、通勤距離が片道2km以上の場合に支給する、特定の交通手段のみを対象とする、といった具体的な基準を設定することが可能になります。
通勤手当の金額設定には、全従業員に一律に支給する方法、通勤にかかる実費を全額支給する方法、または支給額に上限を設けて支給する方法などがあります。
通勤手段別の支給規定
会社は、公共交通機関の利用、自動車・バイク通勤、自転車通勤、徒歩通勤といったいろいろな通勤手段に対して、それぞれの支給基準を設けておくとよいでしょう。
特に、税務上の非課税限度額は通勤手段によって異なるため、これを考慮した規定作りが大切になります。 また、複数の交通手段を併用する場合の取り決めも明確にしておくとよいでしょう。
自動車・バイク通勤の規定
自動車やバイクなど、個通用具を利用する通勤を認める場合、判断基準となるのは自宅から勤務先までの移動距離になります。 その際、交通用具を利用した通勤を認める際の判断としては、電車、バス等の通勤手段が存在しない場合で、且つ、通勤距離が一定以上ある場合と判断する会社が多いでしょう。
交通用具の通勤を認める判断基準となる距離は会社によって異なりますが、 一般的には2km以上であることが一つの基準となるようです。
なぜなら交通用具利用通勤の非課税限度額が、2km未満は全額課税となるためです。
また、自動車通勤は従業員の利便性は向上しますが交通事故のリスクが伴うことから、保険加入有無の確認や、許可制にするなどの対応を定めておくことをお勧めします。
さらに、自動車通勤の場合は駐車場の確保も必要になりますが、駐車場代を通勤手当に含めるかどうかは、状況に応じた対応が必要になるため、別途規定を定めておくことも必要です。
交通用具の非課税限度額や駐車場代の扱い方については次のコラムで説明していますので、併せてご確認ください。
「マイカー通勤者の通勤交通費はどう考えればいい?計算方法のあれこれ」
「駐車場代は通勤手当に含まれる?|課税非課税のルールも」
公共交通機関(電車・バス)通勤の規定
公共交通機関(電車・バス)を利用して通勤する場合も、基本的には自宅から勤務先までの距離によって利用可否を決めることになるでしょう。
バスの利用に関しては、自宅から勤務先までの距離、あるいは自宅から最寄り駅までの距離が規定に定められた距離を超える場合に、利用可能としている会社もあります。
その場合の判断基準となる距離は会社によって異なりますが、2km以上ある場合にバスの利用を可能とする場合が多いようです。
自転車通勤の規定
自転車通勤に関する通勤手当の規定は、会社によって様々です。
一般的に、自転車は所得税法上の「交通用具」に該当します。 自転車通勤を認めるか否かは、自宅から勤務先までの距離で判断するより、駐輪場の確保や交通事故のリスクといったことで判断することが多いようです。
自転車通勤の通勤手当の支給有無についても考え方によって変わります。
支給する場合は、2km未満は全額課税となる点に注意が必要です。
自転車通勤については以下で詳しく説明していますので、併せてご確認ください。
「自転車通勤でも通勤手当は必要?支給額や規則、よくある疑問を解説」
徒歩通勤の規定
自宅から勤務先までの距離が徒歩圏内の場合は、徒歩通勤で勤務することが一般的でしょう。
会社の規定で、徒歩通勤について定義をしている場合もあれば、明確には定義されていない場合もあります。
健康のために、多少離れていても徒歩通勤を行う社員もいるかもしれませんが、 日常的に徒歩通勤を行うことによる身体的な負担や、通勤時間の増加などが懸念事項として考えらますので、
徒歩通勤に関しても距離を決めておくとともに、通勤経路として合理的であることの確認を運用に取り入れておくとよいでしょう。
徒歩の場合の通勤手当の支給有無は会社によってさまざまですが、徒歩の場合は全額課税となる点は留意すべき事項になります。
徒歩通勤に関しては以下で説明していますので、あわせてご確認下さい。
「徒歩で通勤する社員へ通勤手当は必要?|徒歩通勤の扱いについて解説」
Arvoで通勤管理を
今すぐ効率化
通勤距離の測定方法
通勤手当の距離の測定は、各通勤手段の支給条件の判断の基準となるほか、適切な支給額を決定するためにも非常に重要な要素になります。
判断基準の基本となる数値であり、公平な判断をするためにも明確な基準を設けることが求められます。
通勤距離の測り方
通勤距離の測り方には「直線距離」と「道なり距離(経路による距離)」の2つの方法があります。
直線距離とは、自宅と会社の最短距離を直線で結んだ距離を指します。
この測り方は計算が容易である一方、実際の通勤経路と大きく異なる場合があります。
特に、道路はまっすぐではないため、実際の通勤時間や労力と乖離が生じやすいです。
一方、道なり距離は、実際の通勤経路に沿って計測する距離であり、実際に利用する道路に基づいて算出することが一般的です。
マイカーや自転車通勤の場合の所得税の非課税限度額が「通勤経路に沿った長さ」で定められていることから、道なり距離で測定する方がより妥当とされています。
徒歩で通勤する従業員にとっても、往復の通勤にかかる時間を考慮すると、実態に即した道なり距離の採用が望ましいと考えられます。
いずれの測り方を用いる場合でも、会社は就業規則に明確な基準を定めて従業員に周知し、公平な運用を心がけることが望ましいでしょう。
直線距離での算出について
通勤手当の算出において直線距離を採用するのは、測定が比較的容易であるという利点があります。
しかし、実際の道路や経路は直線ではないため、従業員が実際に通勤に要する距離とは大きく異なる場合が多いという課題があります。
直線距離では非常に短いのに、迂回するために実際の通勤距離が大幅に長くなることも考えられます。
このような場合、従業員は実費よりも少ない金額しか通勤手当を受け取れなくなる可能性があり、不公平感を感じることがあります。
また、所得税法上、交通用具の通勤手当の非課税限度額は「通勤経路に沿った長さ」で定められているため、税務上の取り扱いとも乖離が生じる可能性が考えられます。
Arvoで通勤管理を
今すぐ効率化
通勤手当支給時の留意点
通勤手当を支給する際には、いくつかの重要な留意点があります。
まず、支給対象となる最低通勤距離を自社の実態に合わせて設ける必要があります。
正社員と非正規社員間の公平性を確保することも非常に重要です。
また、通勤経路の正確な確認、定期的な見直しなどで、公平性を保ちつつ適切な運用を行うことも大切です。
支給対象となる最低通勤距離
労働基準法には、通勤手当の支給対象となる最低通勤距離に関する明確な規定はなく、企業は自社の通勤実態を考慮して自由に定めることができます。
一般的には片道2km以上を通勤手当の支給対象とする企業が多いとされています。
距離に応じて支給される通勤手当の非課税枠が2km以上から適用されるため多くの企業がこの距離を基準としているのです。
自宅と勤務先が近い従業員に対しては通勤手当を支給しないケースが多いですが、2km未満であっても通勤手当を支給する企業も存在します。
最低通勤距離を設定する際は、徒歩通勤の従業員との公平性を考慮し、従業員間で不公平感が生じないよう慎重に検討することが重要です。
正社員と非正規社員の公平性
通勤手当の支給において、正社員と非正規社員間の公平性を確保することは「同一労働同一賃金」の原則からも非常に重要な基準となります。
労働基準法には通勤手当の明確な規定がないため会社は自由に支給条件を定められますが、 同じ業務を行っているにもかかわらず、雇用形態によって通勤手当に不合理な待遇差を設けることは、2020年4月に施行された同一労働同一賃金制度によって禁止されています。
これは正社員と非正規社員の間で、職務内容や責任の範囲、配置転換の有無などが同じである場合、通勤手当についても同等の支給を行う義務があることを意味します。
企業は、通勤手当の支給基準を策定・見直しする際に、雇用形態に関わらず、通勤実態や業務内容に基づいた公平な基準を設定し、従業員に明確に周知することが求められます。
通勤経路の定期的な見直し
公平性を保ち、かつ適切な金額を支給するためには、通勤経路の定期的な見直しを行う運用も大切です。
まず、従業員が申請する通勤経路が「最も経済的かつ合理的であるか」を確認します。
これは、通勤災害発生時の判断基準にもなるため非常に重要です。
また、従業員が引っ越しをした場合や、公共交通機関の運賃が改定された場合など、通勤経路や費用に変更が生じる可能性がありますが 従業員からの申請遅れがあると、通勤手当支給額の乖離につながるので、定期的に申請内容と実際の通勤状況との整合性を確認する必要があるのです。
まとめ
公共交通機関、交通用具いずれの場合の通勤手段を選択する判断基準としては、自宅から勤務先までの距離を基準とすることが多いです。
通勤距離の測定方法には、自宅と会社を直線で結ぶ「直線距離」と、実際に利用する経路に沿って測る「道なり距離」の2種類がありますが、 交通用具の非課税限度額は「通勤経路に沿った長さ」で定められているため、道なり距離で測定する方法が合理的と考えられます。
また、合理的な通勤手段を選択できるように、最低通勤距離を設定しておくことも大切です。
通勤手当は、従業員が自宅から会社までの通勤にかかる費用を補助する重要な福利厚生です。 通勤距離を正確に判断し、合理的な通勤手段を用いた通勤経路を管理することが求められます。
通勤管理サービスを利用することで、正確な距離の測定、運賃改定などの煩雑な業務を効率化することが望めますので、 一度情報収集をしてみてはいかがでしょうか。
「通勤管理Arvo」では、自宅から勤務地までの距離を道なりルートで測定する方法を採用しています。
「通勤管理Arvo」にご興味がありましたらお問い合わせください。
お問い合わせはこちらから
資料ダウンロードはこちらから
Arvoで通勤管理を
今すぐ効率化