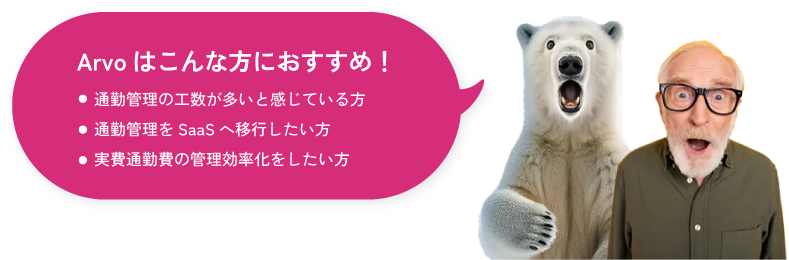定期券の払い戻し計算とは?|通勤定期を解約する方法とそのポイント
通勤などで利用する定期券は、購入時に期間を決めることで通常よりも安価に交通機関を利用できますが、
引っ越しや退職といった理由で不要になった場合は、払い戻しを行うことになります。
払い戻し金額は、使用した期間や購入した定期券の種類によって計算方法が異なっています。
ここでは、定期券の払い戻しに関する計算方法や、通勤利用での解約方法、そして知っておきたいポイントについて解説します。
Arvoで通勤管理を
今すぐ効率化
定期券の払い戻しとは
定期券の払い戻し(解約)とは、有効期間が残っている定期券が不要になった場合に、
定期券の未使用期間に該当する金額を、鉄道会社やバス会社から返金してもらう制度のことを指します。
購入額が全額返金されるわけではなく、使用済みの期間に応じた運賃と手数料が差し引かれた金額が払い戻されることになります。
払い戻しの可否や具体的な金額は、各社の規定や使用状況によって異なります。
払い戻しができるケース
定期券の払い戻しが必要となる主な理由としては、通勤経路の変更、会社の移転、退職、長期出張や休職などにより、定期券の利用が不要になった場合となるでしょう。
鉄道の定期券の場合は、購入した定期券の有効期間が1ヶ月以上残っている場合に、払い戻しが可能となることがほとんどです。
一方で、定期券を誤って購入してしまった場合など、使用開始後の期間が短い場合にも払い戻しが認められることがあります。
バスの定期券の場合は、有効期間内であれば払い戻しが可能です。
いずれの場合でも、払い戻しの際には手数料が差し引かれます。
定期券の払い戻し計算方法
定期券の解約計算方法は、鉄道会社によって異なりますが、一般的には使用した期間に応じた月割り計算が基本となります。
多くの場合、定期券の発売額から使用済みの月数分の定期運賃と手数料を差し引いて払い戻し金額を算出します。
1ヶ月未満の経過日数は1ヶ月として計算されるのが一般的です。
ただし前述の通り、使用開始から7日以内の払い戻しについては、日割りで計算される特例が設けられている場合もあります。
区間変更に伴う払い戻しでは、旬数(10日単位)で計算されることもあります。
また、バス会社の定期券の払い戻しに関しては、月割計算に合わせて、使用した日数換算で解約計算が行われる場合が多いようです。
いずれの場合も、払い戻し金額は、購入した定期券の種類(1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月)や使用した期間によって変動し、払い戻し額が0円となる場合もあります。
Arvoで通勤管理を
今すぐ効率化
1ヶ月定期券の解約計算方法
鉄道の定期券の解約は、原則として有効期間が1ヶ月以上残っていることが条件となるため、払い戻しが難しいケースが多いでしょう。
ただし、使用開始日から7日以内に払い戻しを申し出る場合は、経過日数分に応じ日割利用として払い戻しが可能となる場合があります。
この7日以内日割解約の場合の具体的な計算式は、
「1ヶ月の定期券発売額 – 往復普通運賃×経過した日数分 – 手数料」
で払い戻し額を算出します。
例えば1ヶ月の定期券を1万円で購入し使用開始日から3日後に払い戻した場合、1万円から3日分の往復普通運賃と手数料が差し引かれた金額が払い戻されることになります。
ただし、使用開始から8日以上経過すると1か月分使用したとみなされ、払い戻し額がなくなります。
3ヶ月定期券の解約計算方法
3ヶ月定期券の払い戻し計算は、経過した月数に基づいて行われます。
具体的には、3ヶ月定期券の発売額から、使用済みの月数分の1ヶ月定期運賃と手数料を差し引いた金額が払い戻されます。
例えば、3ヶ月定期券を4月1日に購入し、5月10日に払い戻しを申し出た場合、経過月数は1ヶ月と10日となるため、1ヶ月未満の端数は切り上げて2ヶ月とみなされます。
この場合、3ヶ月定期券の発売額から1ヶ月定期運賃の2ヶ月分と手数料を差し引いた金額が払い戻し額となります。
もし2ヶ月ちょうどで払い戻した場合は、1ヶ月定期運賃の2ヶ月分が差し引かれます。
払い戻し金額がなくなる境界線は、およそ2ヶ月が経過した時点となります。
6ヶ月定期券の解約計算方法
6ヶ月定期券の払い戻し計算も同様に、経過した月数に基づいて行われます。
6ヶ月定期券の発売額から、使用済みの月数分の定期運賃と手数料を差し引いた金額が払い戻し額となります。
使用済みの月数は、1ヶ月未満の端数を1ヶ月として切り上げて計算します。
例えば、6ヶ月定期券を4月1日に購入し、8月20日に払い戻しを申し出た場合、経過期間は4ヶ月と20日となるため、経過月数は5ヶ月とみなされます。
この場合6ヶ月定期券の発売額から、3ヶ月定期運賃と1ヶ月定期運賃の2ヶ月分(合計5ヶ月分)を差し引き、さらに手数料を引いた金額が払い戻されることになります。
経過期間が長くなるほど払い戻し額は少なくなり、およそ5ヶ月が経過した時点で払い戻し額がなくなることが多いようです。
6ヶ月定期券は割引率が高い分、途中解約による払い戻し額は比較的少なくなる傾向があります。
区間変更時の解約計算方法
定期券の区間変更を行う場合は、新たな区間の定期券を購入すると同時に、古い定期券の払い戻し手続きを行います。
この時の解約計算方法は、多くの交通機関で旬割計算が適用されます。
旬とは10日を単位とした期間で、経過した旬数に基づいて払い戻し額が計算されます。
具体的には、古い定期券の発売額から、使用した旬数に定期運賃の日割額を10倍した額を乗じた金額と手数料を差し引いて払い戻し額を算出します。
定期運賃の日割額は、定期券の有効期間(1ヶ月は30日、3ヶ月は90日、6ヶ月は180日など)で
定期運賃を割って計算されます。
ただし、一部の交通機関では区間変更に伴う払い戻し自体ができない場合もあります。
バス定期券の解約計算方法
バス定期券の払い戻し計算は、基本的に鉄道の定期券と同様で、購入した金額から使用済みの期間に応じた運賃と手数料を差し引く方法で行われます。
多くのバス会社では、払い戻し金額は
「購入時の金額 – (定期券の基準運賃 × 2 × 使用日数) – 手数料」
で計算されます。
この「使用日数」は、定期券の通用開始日から払い戻しを行う当日までの日数を指します。
例えば、西鉄バスの通勤1ヶ月定期券を有効期間中に払い戻す場合、この計算式が適用されます。
ただし、計算の結果、1ヶ月定期運賃を超える場合は1ヶ月定期運賃が適用されるなど、バス会社によって計算方法に若干の違いがあります。
また、京王バスのように
「定期券金額 – (普通運賃 × 2回 × 通用開始日から払戻日までの日数) – 手数料」
と明確な計算式を示している会社もあります。
払い戻し手数料は、多くのバス会社で520円から530円程度の手数料が設定されていますが、払い戻し金額が手数料未満になる場合は、払い戻し額がなくなります。
また、バス会社によっては、特定の種類の定期券(例: 年間定期券や一部の割引定期券)は払い戻しができない場合もあります。
払い戻し時の解約手数料
定期券を払い戻す際には、ほとんどの場合で手数料がかかります。
この手数料は、鉄道会社やバス会社によって金額が異なりますが、一般的には鉄道で220円、バスで520円程度が設定されていることが多いようです。
払い戻し金額は、定期券の発売額から使用済み期間に応じた運賃とこの手数料を差し引いて計算されます。
したがって、たとえ未使用期間が残っていても手数料が差し引かれるため、購入金額がそのまま返金されるわけではありません。
特に払い戻し額が少ない場合や、有効期間が残りわずかである場合には、手数料を差し引くと払い戻し額がなくなることもあります。
モバイルSuicaなどのIC定期券の場合も、アプリ上での払い戻し操作で手数料が差し引かれます。
Arvoで通勤管理を
今すぐ効率化
通勤管理における払い戻しのポイント
通勤管理において定期券の払い戻しが発生した場合、会社としていくつかのポイントを押さえておくことが重要です。
従業員が引っ越しや部署異動などで通勤経路が変更になった場合や、退職、休職などで通勤が不要になった場合など、様々な理由で定期券の払い戻し手続きが必要になります。
これらの手続きを円滑に進めるためには、あらかじめ社内での明確なルールを設けておくことが望ましいでしょう。
払い戻しの対象となるケース、手続きの方法、必要書類などを定めておくことで、従業員からの問い合わせに適切に対応できます。
また、払い戻しによって発生した金額の精算方法についても、給与での調整や現金での受け渡しなど、明確な取り決めをしておくことが、経理処理の効率化につながります。
通勤管理システムなどを活用することで、これらの払い戻し計算や精算業務を効率化することが可能です。
会社としての払い戻しに関するルールを明確にし、従業員に周知することが、スムーズな通勤管理を実現するための重要なポイントと言えるでしょう。
払い戻しルールの明確化
通勤管理においては、従業員が定期券の払い戻しを申請する際の条件、例えば、どのような理由であれば払い戻しが可能かなどを具体的に定めます。
また、払い戻し手続きに必要な書類や申請方法についても明確にしておくことで、従業員は迷うことなく手続きを進めることができます。
会社によっては、通勤経路の変更に伴う定期券の区間変更についてもルールを定めている場合があります。
これらのルールを就業規則や通勤費規程などに明記し、従業員に周知徹底することが、円滑な通勤管理業務につながります。
精算方法の取り決め
払い戻された金額の精算方法についても会社として明確な取り決めを行っておきましょう。
従業員が定期券の払い戻しを受けた際に、その金額をどのように会社に返金してもらうのか、あるいは次の通勤費支給額から差し引くのかなど、具体的な精算方法を定めます。
例えば、給与と一緒に払い戻し金額を振り込む、あるいは対面で現金にて受け渡しを行うなど、会社の運用に合わせた方法を取り決めます。
また、払い戻しが行われたタイミングによっては、日割りでの実費支給が必要となる期間が発生する可能性もあるため、その場合の精算方法についても考慮しておくと良いでしょう。
これらの精算方法を社内規定として明確にし、従業員に周知することで、経理担当者の業務負担を軽減し、適切な通勤費の管理を行うことができます。
まとめ
定期券の払い戻しについて理解することは、個人だけでなく通勤管理業務においても重要です。
払い戻しの計算方法は、使用した期間や購入した定期期間によって異なり、多くの場合、経過した月数に応じた月割り計算が基本となります。
また、使用開始後7日以内の払い戻しや区間変更時には特別な計算方法が適用されることもあります。
いずれの場合も手数料が差し引かれるため、購入金額が全額戻ってくるわけではありません。
払い戻しの条件や計算方法、精算方法について明確なルールを定め、従業員に周知することが円滑な手続きのために不可欠です。
通勤管理システムの導入も、計算や手続きの効率化に役立つ方法の一つと言えるでしょう。
「通勤管理Arvo」にご興味がありましたらお問い合わせください。
お問い合わせはこちらから
資料ダウンロードはこちらから
Arvoで通勤管理を
今すぐ効率化