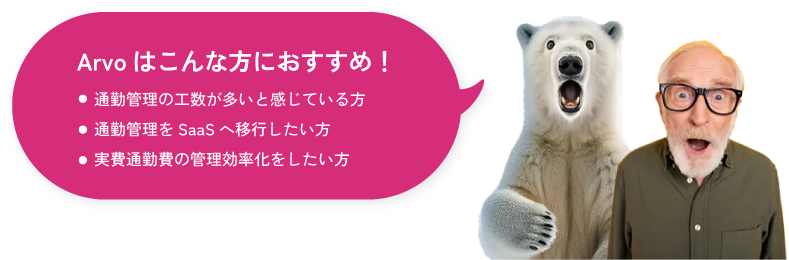通勤手当と労働基準法の関係について|支給規定の考え方も
通勤手当は多くの企業が従業員に支給していますが、労働基準法には通勤手当に関する具体的な規定がありません。 そのため企業は独自の規定を設けて管理を行っています。
本記事では、通勤手当に関する労働基準法の基本的な考え方から、適切な支給規定を定めるための実務的なポイントまで解説していきます。
Arvoで通勤管理を
今すぐ効率化
労働基準法と通勤手当の基本的な考え方
多くの企業が通勤手当を従業員へ支給しています。
しかし労働基準法においては、通勤手当の支給基準や上限額に関する具体的な規定はなく、企業にその支給を義務付けているわけではありません。
これは、通勤手当が法律で定められた義務ではなく、企業の裁量によって自由に規定できる福利厚生の一つであるためです。
ただし、就業規則や労働契約において「通勤手当を支給する」と明記されている場合は、企業にその支払い義務が発生します。
このように、労働基準法は直接的に通勤手当の支給を義務付けていないものの、一度規定を設ければ、その規定に従って支給する責任が生じます。
労働基準法における通勤手当の立ち位置
労働基準法で通勤手当の支給を直接的に義務付ける条文は存在しませんが、労働基準法第11条では、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものを「賃金」と定義しており、 就業規則や賃金規定で支給が定められた通勤手当もこの賃金に該当します。
したがって、企業が通勤手当を支給する旨を就業規則等で規定しているにもかかわらず通勤手当を支給しない場合、それは賃金未払いとして労働基準法違反となる可能性があり、 労働基準監督署の指導対象となることも考えられます。
通勤手当は、社会保険料の算定対象となる賃金総額に含まれるため、その計算においても正確に把握することが求められます。
Arvoで通勤管理を
今すぐ効率化
通勤手当の支給規定を定める時の考え方
通勤手当を支給する際には、企業は明確な規定を設けることが必要になります。
規定を定める際には、支給条件や計算方法、上限額などを具体的に明記することで、スムーズな運用につながります。
テレワークの普及など働き方の多様化が進む中、通勤手当の支給ルールも実態に合わせて見直す必要が生じています。
例えば、定期代一律支給から実費支給への切り替えを検討する企業も増えています。
これらの変更を行う場合も、就業規則や賃金規定にきちんと反映させ、従業員に周知することが大切になります。
通勤手段と支給条件の考え方
通勤手当を支給する際、企業は従業員の多様な通勤手段を考慮し、公平かつ明確な規定を設けることが重要です。
一般的な通勤手段としては、公共交通機関(電車・バス)、マイカー、自転車、徒歩などがあります。
これらの通勤手段に応じて、通勤手当の支給条件や計算方法を具体的に定めます。
公共交通機関を利用する場合、通勤手当は通常、定期券の費用を基に支給されます。
企業によっては「最も経済的かつ合理的と認められる経路」を基準とすることもあります。
複数の経路がある場合は、経済的かつ合理的な経路であれば、複数認められることもあります。
ただし、著しく遠回りな経路は合理的とはみなされません。
マイカーやバイク通勤の場合、通勤手当は一般的にガソリン代や通勤距離を基に算出されます。
自転車通勤の場合も、通勤距離に応じて手当を支給する方法が一般的です。
ただし、片道2km未満の自転車通勤では、支給されても全額が課税対象となるため、支給しないケースもあります。
また、自転車と電車を併用する従業員に対しては、両方の費用を合算して通勤手当を計算する会社もあれば、どちらか一方のみを支給する会社もあります。この場合も非課税限度額には注意が必要です。
徒歩通勤については、国税庁の非課税規定が交通機関や交通用具の使用を前提としているため、通勤手当を支給しても所得税の課税対象となることが一般的です。
会社独自の規定により、通勤距離が2kmを超える徒歩通勤者に対しては手当を支給するケースもあります。
このように、通勤手当の支給は企業の裁量に委ねられていますが、就業規則や賃金規定に詳細なルールを盛り込むことで、従業員の理解を深め、スムーズな運用を図ることができます。
支給額の上限金額の考え方
通勤手当の支給には非課税上限額が定められており、この上限額を超過すると、所得税の課税対象となります。
公共交通機関を利用する場合、非課税上限額は1ヶ月あたり15万円です。 自家用車やバイクで通勤するケースでは、通勤距離に応じて非課税上限額が変動します。
企業が通勤手当の支給上限額を決定する際は、これらの非課税枠を意識することが重要です。
就業規則で定められた通勤手当の支給額が、所得税法上の非課税上限額を超過する場合、その超過分は課税対象となり、従業員の手取り額が減少する可能性があります。
そのため、企業は通勤手当の「上限額」を定める際には従業員の税負担も考慮に入れることが、「通勤手当」に関する「考え方」として望ましいです。
ただし、所得税法上の非課税限度額はあくまで税法上の区分であり、会社が支給する通勤手当の額を制限するものではありませんので、会社独自の「上限額」を設定することができます。
Arvoで通勤管理を
今すぐ効率化
実費支給の考え方
通勤手当の「実費支給」とは、従業員が通勤に実際にかかった費用を会社が後から精算して支払う方法を指します。
これは、従業員が交通費を立て替え、後日会社に請求し、翌月の給与とともに返還されるのが一般的な流れです。
従来の定期券代を一括で支給する形式と異なり、実費支給では出勤日数や利用した交通手段によって毎月の支給額が変動することがありますが、テレワークの普及により出社日数が減少した企業では、定期代支給から実費支給に切り替えるケースが増えています。
実費支給のメリットとしては、企業にとっては勤務実態に合った通勤手当の支給が行える点、従業員にとっては実際に発生した費用を補填してもらえる点が挙げられます。
ただし、従業員は一時的に交通費を立て替える必要があり、毎月の支給額が変動することで社会保険の「随時改定」の対象となる可能性も考えられ、企業は事前にルールを明確に定めておく必要があります。
実費支給額の計算方法は通勤手段によって異なり、公共交通機関の場合は乗車運賃の実費、マイカーやバイク通勤の場合は通勤距離に照らし合わせて会社が定めた距離単価と出勤日数で計算されることが多いです。
まとめ
通勤手当の支給については、労働基準法ではその支給は義務付けていませんが、多くの企業が福利厚生の一環として通勤手当を支給しています。
企業が通勤手当の支給を就業規則や労働契約で定めた場合、それは賃金の一部とみなされ、支給義務が発生します。
したがって、企業は通勤手当の支給規定を明確に定め、従業員に周知徹底することが大切になります。
支給条件の明確化、距離による支給基準の策定、自動車やバイク通勤に関する規定、そして支給額の上限金額や実費支給の考え方を盛り込む必要があります。
通勤手当には所得税の非課税限度額が定められているため、その範囲内で支給額を設定することは、従業員の税負担軽減にもつながります。
働き方の多様化が進む現代において、テレワークの導入などにより通勤手当の支給方法を見直す企業も増加しています。
「通勤管理Arvo」は、勤務実績に合わせた通勤費の実費支給の管理にも対応しています。
「通勤管理Arvo」にご興味がありましたらお問い合わせください。
お問い合わせはこちらから
資料ダウンロードはこちらから
Arvoで通勤管理を
今すぐ効率化