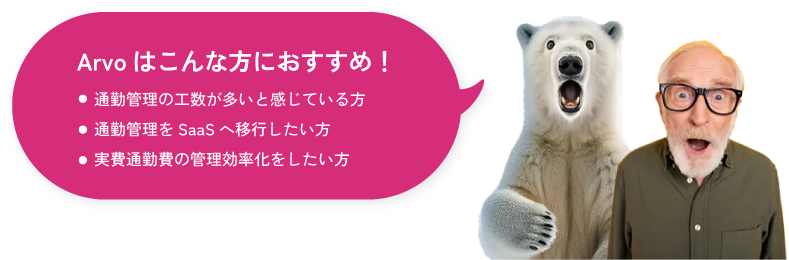派遣社員の通勤手当はどのように支給される?|気になる疑問を解説
以前は派遣社員の交通費は時給に含まれるのが一般的でしたが、現在は原則として通勤手当が支給されるようになりました。
本記事では、通勤手当の支給ルールや支給方式、税金や社会保険料への影響など、派遣社員の通勤手当に関する情報を詳しく解説します。
Arvoで通勤管理を
今すぐ効率化
【結論】法改正により派遣社員も通勤手当が支給されるようになった
2020年4月1日に施行された「労働者派遣法」により、派遣社員にも通勤手当が支給されることが原則となりました。
これは、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差を解消することを目指す
「同一労働同一賃金」の考え方に基づいています。
この法改正に伴い、労働者派遣を行う派遣会社は、派遣社員に対して通勤手当を適切に支給する責任を負うことになりました。
「同一労働同一賃金」の考え方
「同一労働同一賃金」とは、同じ企業内で同じ業務内容に従事する労働者に対し、雇用形態を理由に待遇差を設けることを禁止する原則です。
派遣労働者の場合、比較対象となるのは派遣先で同じ仕事をしている正社員になります。
基本給や賞与だけでなく、通勤手当を含む各種手当もこの原則に含まれます。
派遣会社は派遣先の労働者との均等・均衡を図る「派遣先均等・均衡方式」か、一定の要件を満たす労使協定を締結する「労使協定方式」のいずれかを選択し、派遣労働者の待遇を決定します。
これにより、派遣先の正社員に通勤手当が支給されているのであれば、派遣社員にも不合理な差がないように支給されることになります。
通勤手当の支給方式は派遣会社が決定する
通勤手当の具体的な支給方式は、雇用主である派遣会社が決定します。
同一労働同一賃金の原則に基づき、派遣先の正社員に支給されている方法に合わせることが多いものの、必ずしも同一である必要はありません。
例えば、派遣先の会社では「実費支給」であっても、派遣会社が「定額支給」を選択する場合があります。
重要なのは、通勤手当を含めた全体の待遇において、派遣先の正社員との間に不合理な差が生じないことです。
Arvoで通勤管理を
今すぐ効率化
派遣社員の通勤手当における2つの支給方法
派遣会社が派遣社員に支払う通勤交通費の支給方法には、主に「実費支給」と「定額支給」の2種類が存在します。
実費支給は実際にかかった費用が支払われる方法で、定額支給は毎月決められた金額が支払われる方法です。
どちらの方式が採用されるかは雇用主である派遣会社の規定により決まります。
①かかった交通費を全額受け取れる「実費支給」
実費支給は、自宅から就業場所までの通勤にかかった費用を、派遣会社が実費で支払う方法です。
多くの場合、電車やバスといった公共交通機関を利用する際の、最も経済的で合理的な経路にかかる費用が対象となります。
この方式の利点は、通勤にかかる金銭的な自己負担がなくなる、あるいは大きく軽減されることです。
特に、遠方から通勤する場合や、複数の通勤手段を乗り継ぐ必要がある場合にメリットを感じやすいでしょう。
申請の際には、利用する経路や交通機関を正確に申告し、承認を得る必要があります。
また、転居などで通勤経路が変更になった場合にも、速やかに再申請の手続きを行うことが求められます。
②毎月一定の金額が支払われる「定額支給」
定額支給は、実際の通勤費用に関わらず、毎月一定の金額を通勤手当として支給する方法です。
支給額は派遣会社の規定によって定められており、例えば「月額一律1万円」や「1日500円」のように決められています。
この方式のメリットは、計算がシンプルで分かりやすい点です。
一方で、実際にかかる交通費が支給額を上回る場合は、差額が自己負担となります。
Arvoで通勤管理を
今すぐ効率化
通勤経路の決め方
通勤手当の支給対象となる通勤経路は、派遣会社に申請し、承認を得る必要があります。
一般的に認められるのは、自宅から派遣先までの「最も経済的かつ合理的な経路」です。
これは、移動時間や費用を総合的に判断して最も効率的とされるルートを指し、多くの場合、
最短・最安の経路が基準となります。
新幹線や特急の利用が認められるかどうかは、派遣会社の規定によって異なります。
通勤時間の大幅な短縮につながるなど、合理的な理由があれば認められるケースもありますが、追加料金は自己負担となることも多いでしょう。
承認された経路以外で通勤した場合は、その分の通勤交通費は支給されない可能性もあります。
通勤手当をもらう前に知っておきたい3つの注意点
派遣社員が通勤手当を受け取る際には、事前に知っておくべき注意点として、 雇用契約を結ぶ前の支給条件の確認、所得税の非課税限度額、そして社会保険料への影響といった観点は重要です。
ここでは、通勤手当に関連する3つの重要なポイントを解説します。
雇用契約を結ぶ前に支給条件を確認
派遣会社と雇用契約を結ぶ前に、通勤手当の支給条件を詳細に確認することが不可欠です。
確認すべき項目には、支給の有無、支給方法(実費か定額か)、上限額、対象となる交通手段(公共交通機関のみか、自家用車も可能か)、申請手続きの方法などが含まれます。
例えば、バスの利用は自宅から駅まで2km以上離れている場合のみ対象、といった細かい規定が設けられている場合もあるでしょう。
疑問点があれば、契約前に担当者に確認をして明確にしておくことが望ましいです。
口頭での確認だけでなく、雇用契約書や就業規則に記載されている内容をしっかりと確認しておきましょう。
所得税の非課税限度額について
通勤手当は、一定の金額までは所得税が課税されない非課税扱いとなります。
公共交通機関を利用する場合は1ヶ月あたり15万円が上限です。
自動車や自転車の場合は、片道の通勤距離に応じて非課税限度額が定められています。
この限度額を超えた金額は給与所得とみなされ、課税の対象となります。
なお、同一労働同一賃金の「労使協定方式」では通勤手当を時給に上乗せして支払うケースもあり、
例えば全国平均の通勤手当額を基に算出した時給72円(2020年度の例)といった額が加算されることがあります。
この場合も、非課税限度額のルールは同様に適用されます。
社会保険料の負担額への影響について
通勤手当は、社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料など)の算定基礎となる「標準報酬月額」に含まれます。
これは、所得税のように非課税枠が設けられておらず、支給された通勤手当の全額が対象となります。
そのため、通勤手当が支給されることによって標準報酬月額の等級が上がると、毎月の社会保険料の自己負担額が増える可能性があります。
社会保険料の負担は増えますが、一方で、将来受け取る厚生年金の金額が増加したり、傷病手当金などの給付額が増えたりするという側面も持ち合わせています。
社会保険と通勤手当の関係については、以下コラムで詳しく紹介していますので、あわせてご参照ください。
「通勤手当と社会保険料、どう関係している?|その計算方法について」
「通勤手当の変更時には社会保険料の随時改定が必要?|条件と注意点を解説」
まとめ
2020年4月の法改正により、「同一労働同一賃金」の原則が適用され、人材派遣の社員にも原則として通勤手当が支給されるようになりました。
支給方法には「実費支給」と「定額支給」があり、どちらが採用されるかは雇用主である派遣会社の規定によります。
実費支給の場合、「最も経済的かつ合理的な経路」が通勤経路として採用されることになります。
通勤手当は一定額まで所得税が非課税となる一方、社会保険料の算定基礎には全額が含まれるため、手取り額や将来の年金額に影響を与えることからも、 派遣社員への通勤経路や通勤手当額の正確な管理が求められます。
「通勤管理Arvo」にご興味がありましたらお問い合わせください。
お問い合わせはこちらから
資料ダウンロードはこちらから
Arvoで通勤管理を
今すぐ効率化