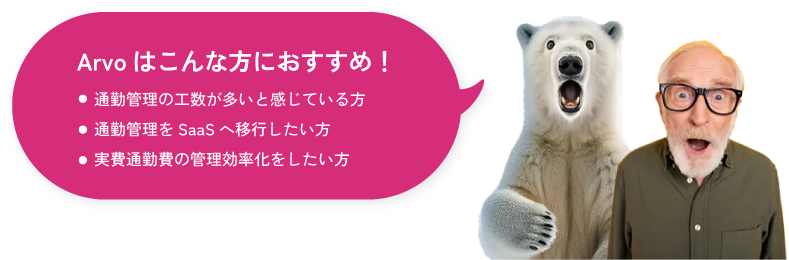社有車での通勤利用は可能?|通勤手当の扱いや会社が定めるべきルールを解説
社有車(社用車)の通勤利用は企業にとってメリットがある一方、リスクも伴います。
許可する際には通勤手当の扱いや費用負担、税務上の注意点を理解し、車両管理規程で明確なルールを定めることが大切です。
この記事では、社有車の通勤利用に関するメリット・デメリットから、規程に盛り込むべき具体的な項目、安全管理の方法までを解説します。
Arvoで通勤管理を
今すぐ効率化
社有車での通勤が認められる主なケース
社有車での通勤が認められるのは、特別な事情による場合が多いでしょう。
例えば、公共交通機関での通勤が困難な地域に事業所がある場合や、早朝・深夜の勤務で公共交通機関が利用できないケースが考えられます。
また、営業職などで自宅から直接取引先へ向かう「直行」や、取引先から直接自宅へ帰る「直帰」が頻繁に発生する従業員に対しても、 業務効率化の観点から通勤利用が許可されることがあります。
会社が社有車の通勤利用を許可するメリット
社有車の通勤利用を許可することは、企業と従業員の双方にメリットがあります。
従業員にとっては通勤の負担が軽減され、特に公共交通機関が不便な地域では通勤の利便性が大幅に向上します。
企業側としては、従業員の通勤ストレスを減らすことができ満足度向上につながるほか、採用活動においてもアピールポイントとなりえるでしょう。
また、災害時や緊急時においても、従業員が迅速に出社できる点や、直行直帰を認めることで業務効率化を図れる点も大きな利点です。
知っておくべき社有車を通勤利用させるデメリットとリスク
しかしながら、社有車の通勤利用を許可することはメリットだけでなく、企業が負うべきデメリットやリスクも存在します。
最も大きなリスクは、通勤中に発生した事故の責任問題です。
また、車両の盗難やいたずら、従業員による私的利用の横行といった問題もリスクとして想定しなければなりません。
社有車の通勤利用を円滑に運用するため、事前にリスクを洗い出し把握し、車両管理規程の整備や保険の見直しなどの対策を講じることが重要になります。
Arvoで通勤管理を
今すぐ効率化
通勤中の事故発生リスク
社有車の通勤利用を許可する場合、最も注意するべき事柄は通勤中の事故発生リスクです。
業務時間外の通勤中に従業員が事故を起こした場合でも、企業は使用者責任を問われる可能性があります。
特に、人身事故の場合は被害者への損害賠償が高額になるケースも少なくありません。
また、事故によって車両が損傷すれば修理費用が発生し、その期間中は業務に支障が出ることもあります。
企業としては、任意保険の適用範囲を通勤中もカバーできる内容に見直し、従業員に対して定期的な安全運転教育を実施することが不可欠になるでしょう。
事故発生時の報告ルートや対応手順を規程で明確化し、いざという時に迅速な対応ができる体制を整えておくことも重要です。
車両の盗難やいたずらに遭う可能性
社有車を従業員の自宅で保管する場合、会社の駐車場に比べてると防犯管理が行き届きにくく、盗難やいたずら等のリスクが高まります。
車両が盗難されてしまうと代替車両の手配や新規購入など、多額の費用が発生するだけでなく業務に大きな支障をきたします。
また、車内に重要な書類、顧客情報が入ったPCなどを保管していた場合は、情報漏洩という二次被害につながる恐れもあります。
このような事態を防ぐために、従業員に防犯対策が施された駐車場を確保させることや、車内に貴重品を放置しないよう指導を徹底することが重要になります。
また、車両保険の内容を確認し、盗難が補償の対象となっているかどうかも事前に確認しておきましょう。
私的利用と業務利用の線引きが難しい
社有車の通勤利用を認めると、業務利用と私的利用の境界が曖昧になりやすいのも課題のひとつです。 通勤の途中で買い物に立ち寄る、休日に家族の送迎に使うなど、従業員が悪意なく私的に利用してしまうケースは考えられますが、 このような私的利用中に事故が発生した場合、保険の適用が受けられない可能性、事故の責任の所在が複雑化するリスクがあることは念頭に置くべきでしょう。
また、私的利用分のガソリン代を会社が負担することになれば、経費の不正利用につながります。
私的利用のリスクを防ぐため、車両管理規程で私的利用を明確に禁止し、業務外での利用範囲を具体的に定めておきましょう。
走行日報の提出を義務付け、走行距離や給油記録を管理することで、私的利用を抑制する効果も期待できます。
Arvoで通勤管理を
今すぐ効率化
社有車通勤における費用負担の考え方【通勤手当】
社有車の通勤利用では、ガソリン代や駐車場代といった費用を会社と従業員のどちらが負担するか、明確に定める必要があります。
また、これらの費用を通勤手当(通勤費)として支給するのか、実費精算とするのかによって、経費処理や税務上の扱いが異なるため注意が必要です。
ルールが曖昧のままだと、企業と従業員との間でトラブルに発展する可能性があり、円滑な運用のためにも費用負担に関する具体的なルールを事前に整備しておくことが重要になります。
通勤にかかるガソリン代は誰が負担する?
社有車通勤にかかるガソリン代の負担については、会社が全額負担する場合と、従業員が一部または全額を負担する場合が考えられます。
一般的には、通勤距離に応じて会社が定める単価を基に算出した金額を通勤手当(通勤費)として支給するケースが多いです。
この際、自宅から会社までの合理的な通勤経路を事前に申請させ、その距離に基づいて計算するのが公平な方法といえます。
あるいは、給油は会社指定の法人向け給油カードを使用、給油記録の提出を義務付けるといった運用管理も管理が容易となります。
どのような方法を選択するにせよ、規程で負担区分を明確に定めておくことがトラブル防止の鍵になります。
有料道路利用のルール
有料道路の通勤利用については、業務上の必要性に応じて会社が負担するケースが一般的になります。
その場合、ETCカードを従業員に貸与するか、従業員が立て替えた費用を後日精算する形を取ることが多いです。
精算する際は、利用区間と金額がわかる領収書やETC利用明細の提出を義務付けるなど、明確性を担保するよう運用を行います。
一方、通勤時間短縮のためだけに有料道路を利用する場合も考えられますが、それが合理的な通勤経路とみなされない場合には、従業員が自己負担するといったルールを設けることも可能です。
公平性を保つためにも、有料道路の利用に関する判断基準や費用負担のルールを通勤規程に明確に盛り込み、従業員に周知するようにしていきましょう。
自宅の駐車場代は経費にできるのか
従業員が自宅で社有車を保管するために借りる駐車場の代金は、原則として会社の経費(地代家賃など)として計上できます。
ただし、経費として認められるためには、その駐車場が社有車の保管に必要不可欠な理由が必要になります。
例えば、会社が従業員に社有車の自宅保管を命じている場合や、自宅周辺に会社の駐車場がない場合などが該当します。
会社が駐車場代を負担する場合は、従業員が会社名義で契約するか、従業員が立て替えた費用を会社が精算する形をとります。
従業員が駐車場代を負担し、会社がその費用を通勤手当(通勤費)に含めて支給することも可能ですが、その場合は給与として扱われ、従業員の所得税や社会保険料へ影響がでてくる可能性があるため、処理方法は事前に明確にしておきましょう。
通勤手当として支給する場合の課税について
社有車での通勤費用を通勤手当として従業員に支給する場合、税務上の非課税限度額が定められています。
この非課税限度額は、片道の通勤距離に応じて段階的に設定されており、限度額を超える部分については給与所得として課税対象です。
非課税限度額については
「マイカー通勤者の通勤交通費はどう考えればいい?計算方法のあれこれ」
で詳しく説明していますので、併せてご参照ください。
企業は、従業員から申告された通勤距離が合理的なものであるかを確認し、非課税限度額を超えて支給する場合には、その超過分を給与に含めて源泉徴収を行わなければなりません。
また、ガソリン代を実費精算する場合や、会社が法人契約した給油カードで支払う場合は、通勤に必要な合理的な金額であれば、現物給与として課税されることはないとされています。
Arvoで通勤管理を
今すぐ効率化
トラブル回避のために車両管理規程で定めるべき6つのルール
社有車の通勤利用を許可する際には、トラブルを未然に防ぐために詳細なルールを定めた車両管理規程の整備が不可欠です。
この規程には、利用の範囲や費用負担、事故発生時の対応などを具体的に明記し、従業員に周知徹底することが求められます。
明確な規定を設けることで、私的利用の防止や事故時の責任問題の明確化につながり、企業のリスクを低減させることができます。
ここでは、規程に盛り込むべき特に重要な6つのルールについて解説します。
1. 通勤に利用できる経路を限定する
車両管理規程において、通勤に利用できる経路をあらかじめ定めておくことは、リスク管理の観点からも非常に重要です。
従業員に自宅から会社までの最も合理的かつ安全な経路を申請させ、会社がそれを承認する形で運用するのが一般的です。
通勤経路を定めておくことで、従業員が通勤の途中で不必要な場所に立ち寄るなどの私的利用を抑制する効果も期待できます。
通勤経路を限定することで、万が一事故が発生した場合に、それが承認された経路上の出来事であったかどうかを明確にでき、労災認定や保険適用の判断がスムーズになります。
経路から大きく外れた場所での事故は、通勤災害と認められない可能性があるため、従業員保護の観点からもこの規定は重要になります。
また、事故や工事中によって通行できないケースも想定されますので、そういう場合の対応についてもルール化しておくととっさの判断がつきやすくなるでしょう。
2. 業務目的以外での使用を明確に禁止する
社有車の私的利用はさまざまなトラブルの原因となるため、車両管理規程で業務目的以外での使用を明確に禁止する規定を盛り込むことが抑止力として有効になります。
具体的には「通勤および業務遂行の目的以外での使用を一切禁ずる」といった文言を明記します。
これには、休日のレジャー利用や家族の送迎、通勤経路から逸脱しての買い物などが含まれます。
この規定を設けることで、私的利用中に発生した事故の責任が会社に及ぶリスクを低減できます。
また、ガソリン代などの経費が不正に利用されることを防ぐ効果もあります。
規定の実効性を高めるためには、単に禁止するだけでなく、違反した場合の罰則(懲戒処分など)についても定めておくとともに、走行日報などで車両の利用状況を定期的に確認する体制を整えることが望ましいです。
Arvoで通勤管理を
今すぐ効率化
3. 事故が起きた際の責任の所在を明らかにする
万が一、通勤中に社有車で事故が発生した場合、その責任の所在を巡って会社と従業員の間でトラブルになる可能性を避けるため、 車両管理規程で事故発生時の責任分担を明確に定めておく必要があります。
一般的には、従業員に重大な過失(飲酒運転、無免許運転、著しい速度超過など)がない限りは会社が加入する自動車保険で対応し、 修理費用の自己負担分(免責金額)や保険でカバーできない損害について、会社が負担する場合が多いです。
ただし、従業員の過失の程度に応じて、一部を本人に負担させるという規定を設けることも可能です。 どのような場合に誰が、どの程度の責任を負うのかを具体的に記載することで、万が一の事態にも冷静かつ迅速に対応できるようになります。
4. 交通違反の罰金は運転者本人が支払う
通勤中や業務中に発生した交通違反に関する責任の所在も、車両管理規程で明確にしておくべき事項です。
駐車違反やスピード違反などの交通違反に対する反則金や罰金は、運転行為者である従業員本人の責任であり、会社が負担すべきものではありません。
そのため、規程には「交通違反に関する反則金および罰金は、すべて運転者本人が負担する」という趣旨の規定を明記する必要があります。
特に駐車違反の場合、放置違反金が車両の所有者である会社に請求されることがあるため、違反した従業員に速やかに警察へ出頭させ、手続きを行うよう義務付ける規定も重要です。
会社が立て替えた場合でも、後日従業員に求償することを定めておけば、トラブルを未然に防ぐことができます。
5. 許可された本人以外の運転を禁止する
社有車の運転者を限定することは、リスク管理の基本です。
車両管理規程には、会社が通勤利用を許可した従業員本人以外の運転を厳しく禁止する規定を盛り込む必要があります。
家族や友人、知人などが社有車を運転し、万が一事故を起こすといったケースも考えられ、会社が多額の損害賠償責任を負うことになりかねません。
また、運転者の運転技量や運転歴を会社が把握していないため、事故のリスクも高まります。
規程で「いかなる理由があっても、許可された者以外の運転を禁止する」と明記し、違反した場合は懲戒処分の対象となることを示しておくことで、ルール遵守の意識を高めることができます。
この規定は、車両の安全な運用と企業の責任範囲を明確にする上で非常に重要です。
6. 走行距離や給油記録の報告を義務化する
社有車の適正な利用を管理するためには、利用状況を客観的なデータで把握することが不可欠です。
そのため、車両管理規程に走行日報の作成と提出を義務付ける規定を設けることが推奨されます。
走行日報には、運転日、運転者、始業時と終業時のメーター距離、走行距離、目的地、給油量などを記録するようにします。
これにより、私的利用の有無を確認しやすくなるだけでなく、ガソリン代などの経費が適正に使われているかをチェックできます。
また、走行距離を把握することで、オイル交換やタイヤ交換といった車両のメンテナンス時期を適切に管理し、車両のコンディションを良好に保つことにもつながります。
Arvoで通勤管理を
今すぐ効率化
安全管理を徹底するための具体的な対策
社有車の通勤利用を安全に運用するためには、車両管理規程を整備するだけでなく、具体的な安全管理対策を講じることが重要です。
事故を未然に防ぎ、万が一の際に企業と従業員を守るためには、 ドライブレコーダーの設置の活用は、客観的な記録を残し、従業員の安全運転意識を向上させる上で有効な手段となります。
ドライブレコーダーの設置で万が一の事故に備える
すべての社有車にドライブレコーダーを設置する対策は、事故発生時のリスクを軽減するために極めて有効な対策です。
ドライブレコーダーは事故の瞬間を映像と音声で記録するため、事故原因の究明や過失割合の判断において客観的な証拠となります。
これにより、事実と異なる主張によるトラブルを回避できる可能性が高まります。
また、映像が記録されているという意識は、従業員の安全運転への意識向上にもつながり、危険運転や交通違反の抑止力としても機能します。
近年では、前方だけでなく後方や車内を撮影できるモデルや、衝撃を検知して自動的に録画を開始・保存する機能、通信機能を備えリアルタイムで映像を確認できる製品も登場しているので、最適な機器選定をおこなえるようになっています。
まとめ
社有車の通勤利用は、業務効率化や従業員満足度の向上といったメリットがある一方で、事故のリスクや管理コストの増大といったデメリットも存在します。
社有車の通勤利用を許可する際には、これらのメリットとデメリットを十分に比較検討し、自社の状況に合った運用とすることが大切になってきます。
導入を決めたら、利用範囲、費用負担、事故時の責任の所在などを定めた詳細な車両管理規程の策定が、トラブルを未然に防ぐために不可欠になります。
通勤利用の経路は、合理的な経路を事前に定めておくことで、万が一事故が発生した場合、労災適用時にスムーズに対応することができます。
さらに、ドライブレコーダーの設置、従業員への安全教育を徹底することで、リスクを最小限に抑えながら制度を運用することが可能になります。
「通勤管理Arvo」は、車ルートの合理的な経路を自動判定でき、適切なガソリン代を算出することができます。
「通勤管理Arvo」にご興味がありましたらお問い合わせください。
お問い合わせはこちらから
資料ダウンロードはこちらから
Arvoで通勤管理を
今すぐ効率化