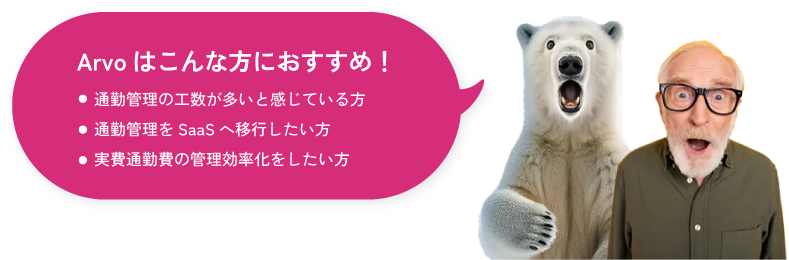徒歩で通勤する社員へ通勤手当は必要?|徒歩通勤の扱いについて解説
徒歩で通勤する社員へ通勤手当は必要?|徒歩通勤の扱いについて解説
徒歩通勤の場合は交通費が発生しないため、多くの企業では徒歩通勤者を通勤手当の支給対象外としているのではないでしょうか。
しかし、企業によっては、徒歩通勤への通勤手当を支給している場合もあります。
当記事では、徒歩通勤への通勤管理のポイントを確認します。
Arvoで通勤管理を
今すぐ効率化
徒歩通勤時の通勤手当の基本
徒歩通勤者に対しても手当を支給する企業がありますが、どのような判断で徒歩通勤への通勤手当を支給しているのでしょう。
徒歩通勤とは何か
徒歩通勤とは、社員が自宅から勤務先までの移動を徒歩で行うことを指します。交通機関や車両を利用せず、直接歩いて通勤するスタイルで、通勤距離が短い場合に徒歩通勤を行うことが多いでしょう。
徒歩通勤の大きなメリットは、交通費がかからず経済的である点です。また、通勤による日常的な運動により健康維持や生活習慣病の予防にもつながる場合があります。通勤距離が徒歩で無理なく移動できる範囲であれば、ストレスを感じず通勤できることも利点です。
反面、距離が長い場合には肉体的負担が大きく、疲労や時間的な制約も発生します。
また、悪天候の日や、夜間の徒歩通勤は安全面でのリスクがあります。
企業としては、徒歩通勤者に対して、どのような距離や条件の場合に通勤手当を支給するのか、就業規則などで明確に定めておくことが重要です。
会社が通勤手当を支給する必要性
企業には通勤手当を支給する法的義務はありませんが、多くの企業では福利厚生の一環として支給しています。
そこには、通勤にかかる費用の負担を軽減し、従業員の生活を支えるという目的も含まれます。
公共交通機関や自動車を利用する社員の通勤手当は必ず発生するしますが、徒歩通勤者には交通費が発生しないことが多く、徒歩通勤への通勤手当支給の有無や基準は企業の裁量で定めていることが一般的です。
企業が通勤手当の支給方針や方法を決定する場合は、社員の通勤に伴う負担が多様であることを考慮しながら、公平な規定を整えることが求められます。
徒歩の場合の通勤手当 支給の実態
一般的に徒歩通勤については、交通費を支給しないケースが多いですが、一部の企業では社員への福利厚生を重視して、独自に通勤手当を支給していることもあります。
徒歩でも支給対象になるか
徒歩通勤の場合、通勤手当の支給対象外とされることが一般的なのは、所得税法の観点から見て、通勤手当は給与所得者が通勤時に利用する公共交通機関や、自家用車など交通用具を利用する際の費用に対して支給されることが想定されているためです。
そのため、徒歩通勤では通常、通勤手当の支給は行われません。
ただし、企業によっては、徒歩通勤の場合の身体的負担や通勤時間の長さなどを考慮して、手当を支給するケースもあります。
徒歩通勤における距離の扱い
徒歩通勤においては、距離が通勤手当支給の基準となる重要なポイントになります。
2kmを超える距離を日常的に歩く場合、身体的負担や通勤にかかる時間の増加が懸念されるため、通勤距離が2km以上の場合に限定して、徒歩通勤手当の支給対象とするケースがあります。
なお、距離の計測方法については、最短ルートや実際に利用するルートを基準として、企業として統一された基準を設けて算出されることが一般的です。
他の通勤手段との比較
徒歩通勤と異なり、他の通勤手段は通勤手当の支給基準が明確に定められていることが多いです。
公共交通機関を利用する場合は、定期券(定期)の料金や乗車区間・区間距離を基に通勤手当が支払われるのが一般的で、正社員だけでなくパートやアルバイトの場合もその基準に沿って支給される場合があります。交通用具での通勤では、実際の交通費や通勤距離に応じて金額が設定され、ガソリン代や駐輪場代の支給ルールが設けられていることも多いです。
それぞれの通勤手段の特徴や利用状況に合わせて、適切な通勤手当制度を導入することが大切です。
バス通勤時の支給基準
バス通勤の場合、通勤手当の支給額は多くの場合、実際に利用するバスの定期券代やバス運賃に基づいて決定されます。
多くの企業では、通勤経路として最も合理的なバス路線を選択し、その定期券の料金または通常運賃を通勤手当の対象としています。バス定期を利用している場合は、その定期代が支給額の基準となるケースが一般的です。
もし通勤経路が一定でなくバス路線を複数利用する場合には、バス運賃の標準的な経路や平均的な運賃で通勤手当を算出することがあります。
会社の就業規則には、バス通勤における通勤区間、定期券利用時の支給額の上限、支給方法などを明確に規定しておくことが重要です。
最近ではICカードをはじめとする交通系電子マネーでバスを利用するケースも多いため、利用履歴を確認してバス通勤の実態と定期の有無を把握する場合もあります。
このような運用を行うことにより、不正受給を防ぐこともでき、バスの利用実態に即した通勤手当の正確な支給が可能になります。
自転車利用の場合
自転車通勤に対する通勤手当の支給は、多くの企業において徒歩や公共交通機関とは異なる独自の基準が設けられることが多いです。自転車は「交通用具」として正式に認識されているため、通勤距離に応じて手当が支給されることが一般的です。
具体的には、1キロメートルあたり一定額を掛け合わせる従量制や、月ごとに定額を支給する方式が多く採用されています。
また、道路交通法の改正に伴い、自転車利用者に対する安全教育や違反に対する罰則が厳格化されている背景から、企業としては通勤ルートの安全確認や違反防止に努める必要があります。
このため、通勤用の自転車が適切に管理されているか、定期的な通勤経路の確認が推奨されます。
自転車通勤ではガソリン代のような燃料費は発生しませんが、駐輪場代などの費用がかかるため、それらを補助する目的の手当という側面が強いと言えるでしょう。健康促進や環境保護の観点から、自転車通勤推進を掲げる企業が増える中、こうした手当は福利厚生の一環として従業員満足度の向上にも寄与しています。
一方で、支給基準は企業によって異なり、距離の算定方法や支給額の設定には、明確な規定を就業規則内で示すことが不可欠です。
実際に、定期的に通勤経路や距離を確認し、違反行為や不正申請の発見につなげる管理体制が整備されているケースも増加しています。このように、安全面の配慮を含めた体系的な管理が、自転車通勤手当を適正に運用するうえで重要となっています。
通勤手当の課税ルール
通勤手当は、一定の範囲内であれば所得税の非課税対象となります。
非課税限度額は国税庁の基準に従い、支給額がこの非課税限度額を超えた場合、超過分は課税対象となり、給与所得として課税されます。
通勤手当における課税・非課税のルールは複雑な場合が多いため、誤った税務処理を防ぐためにも、最新の法令や国税庁のガイドラインを随時確認しながら、適切な対応を心がけましょう。
徒歩通勤に対する課税の考え方
国税庁のガイドラインに基づくと、通勤に必要な交通機関または交通用具の使用にかかる費用が非課税対象として認められており、徒歩はこれに該当しません。そのため、実際に通勤交通費が発生しない徒歩通勤に対して通勤手当を支給した場合、その支給額は所得税の課税対象となります。
そのため、企業と従業員双方にとって負担増となる可能性があります。
たとえば、徒歩通勤者に月額1万円の手当を支給した場合、その全額に所得税負担が発生します。
公共交通機関を利用する従業員の通勤手当は15万円までの非課税限度額が設けられていることから、同一手当を支給した場合でも非課税となり、課税・非課税の取扱いには明らかな違いがあります。
徒歩通勤への通勤手当を導入する際は、企業の財政状況や従業員の負担軽減の視点も重要ですが、課税対象であることを踏まえた金額設定と税務処理を適切に行う必要があります。
通勤手当の課税と非課税要件の整合性を正確に把握することは、税務リスクを回避するうえで重要です。
他の交通手段と課税条件の違い
公共交通機関や自家用車、自転車、バスなどを利用した通勤手当の課税条件は、徒歩通勤とは異なり、
実際にかかる通勤手当に基づいて非課税範囲が設定されており、非課税限度額以内の支給であれば所得税は課されません。
ただし、非課税限度額を超えた部分の手当は同様に給与所得として課税対象として取り扱われます。そのため、企業は定期やバスなど各交通手段ごとの利用実態や料金体系を考慮して適正な上限設定を行う場合もあります。
また、自家用車通勤の場合は、ガソリン代の支給条件を非課税限度額を考慮しながら、明確に設定することが求められす。
定期やバス、自転車など利用する交通手段ごとの課税ルールをしっかりと理解し、支給基準を適切に整備することが大切です。
通勤手当支給における企業に求められる注意点
通勤手当を支給する際には、適切な管理と基準の設定が必要です。
特に、徒歩通勤者を含めた支給範囲の明確化がポイントになります。
また、通勤手当の不正受給を防止するためにも、通勤ルートや利用交通機関の申請内容をしっかり確認することも重要です。
不正受給の防止策
通勤手当の不正受給を防止する具体的な対応としては、従業員が申告した通勤ルートや通勤手段の定期的な確認が有効です。
例えば、通勤に使用する定期券の提示を求めたり、利用している交通機関やそのルートの報告を徹底させることで、実際の通勤状況と申請内容の不一致を早期に発見できます。
その他、申請プロセス手順を明確に定義して、申請内容の虚偽を見抜くためのチェック体制を運用かすることは、不正受給を抑止するには大切な作業になります。
近年では、ICカードの利用履歴から通勤ルートを正確に把握する企業も増えており、客観的な証拠に基づく監査が効果的な不正防止策となっています。
また、不正受給が判明した場合の具体的な処分規定を就業規則に盛り込み、従業員に周知することも効果的です。
このような包括的な対策を実施することで、通勤手当の不正受給を未然に防ぎ、適正な手当支給を維持することにつながります。
就業規則に明記する重要性
通勤手当の支給に関するルールを、会社の就業規則へ具体的に記載することも重要です。
例えば、従業員・パート・アルバイトを含む全てのスタッフに対し、通勤手段や距離の基準、金額の決め方などを明文化することで、理解が得やすくなります。特にパートやアルバイトのように雇用形態が異なる場合の支給基準を明確にしておくことがトラブル防止につながります。
また、通勤手当の非課税範囲や課税対象の扱いについても会社の就業規則で適切に示しておくことで、税務上のトラブル回避ができます。ルールが曖昧だと、受給条件に関する誤解につながる可能性もあります。
詳細な規定を就業規則に盛り込むことで、担当者による対応のばらつきも出ず、業務対応に一貫性が生まれます。
まとめ
徒歩通勤に関する通勤手当の扱いは、企業ごとに異なる制度となっています。
多くの企業では、徒歩通勤者に対しては基本的に通勤手当の支給は行わない場合が多いですが、徒歩通勤に要する時間・負担の大きさを踏まえ、一部では一定額の手当を付与するケースも見られます。
ただし、税務上の取り扱いにおいては、徒歩通勤の通勤手当は非課税の対象外となり、課税所得として扱われる点に留意が必要となります。
課税される手当の増加が従業員に与える影響も考慮し、企業は支給額の設定や運用ルールについて慎重な判断を行うことが必要です。
また、徒歩通勤者以外の通勤形態との公平性を保ちつつ、就業規則に具体的な規定を盛り込むことで、支給基準の透明化とトラブル防止に繋がるでしょう。
このような複合的な要素を踏まえ、企業は徒歩通勤者が安心して通勤できる環境整備に努めると同時に、通勤手当の支給ルールを体系的に整備することが重要です。働き方の多様化が進む中で、通勤手当制度も柔軟に対応し、社員の生活支援と企業運営の両立を目指すことが求められています。
「通勤管理Arvo」では、徒歩通勤経路の正確な移動距離を自動判定いたします。ルートの把握や適切な通勤手当管理を実現します。
「通勤管理Arvo」にご興味がありましたらお問い合わせください。
お問い合わせはこちらから
資料ダウンロードはこちらから
Arvoで通勤管理を
今すぐ効率化