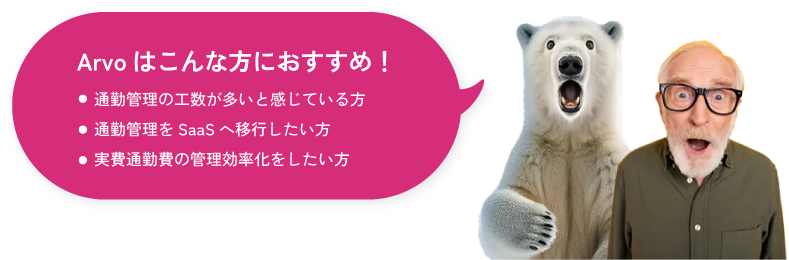通勤手当に課税されているのはなぜ?!所得税と通勤手当の関連について
通勤手当と課税の関係について
通勤手当とは従業員が職場へ移動する際に発生する通勤費の負担を軽減するために支給されるもので、非課税枠のある手当になりますが、一定の金額や条件を超える場合には所得税の課税対象となります。
給与明細を確認したとき「なぜ通勤手当に課税されているのだろう?」と疑問に思う方もいるでしょう。
これは、通勤手当が非課税となる場合と課税される場合が分かれていることが関係しています。
通勤手当の税務処理でなぜ非課税となるのか、またどのような場合に課税されるのかを解説します。
Arvoで通勤管理を
今すぐ効率化
通勤手当は課税の対象?
通勤手当は、一般的に給与の一部として扱われ、所得税の課税対象となります。
ただし、国税庁のガイドラインに基づき、一定の条件を満たす場合には非課税となる特例が設けられています。
通勤手段が合理的かつ経済的であることや、支給金額が国の定める非課税限度額の範囲内ならば非課税になります。
逆に、非課税限度額を超えた部分や、合理性が確認できない通勤経路、徒歩のみの場合などは課税対象になります。
通勤手当と税金について
通勤手当は企業が独自に設けている手当であり、支給の有無や支給金額、条件は企業ごとに異なります。
公共交通機関利用者は全額支給する、マイカー通勤者には上限1万円までを支給する、
あるいは通勤手段を問わず全従業員に一律で支給するなど、支給方法はさまざまです。
具体的な支給ルールについては、必ず勤務先の就業規則や規定を確認するようにしましょう。
また、通勤手当は給与所得の一部として扱われますが、所得税および住民税は、国税庁が定める非課税限度額以内であれば課税されません。
ただし、非課税限度額を超える部分については、課税対象として計算され、会社が源泉徴収を行うことになります。
そのため、限度額を超える通勤手当を受け取っている場合は、所得税と住民税が発生することになります。
通勤手当の非課税限度額
通勤手当への税金額を理解するためには、国税庁が定める非課税限度額を理解しておく必要があります。
非課税限度額は、通勤にかかる実際の費用や通勤手段・通勤距離など、いくつかの要件に基づいて設定されています。
非課税限度額以内で支給される通勤手当には所得税がかかりませんが、超えた部分は給与所得として課税対象となります。
また、公共交通機関、自動車などの交通用具、またはこれらの併用による通勤など、方法や通勤距離ごとに非課税限度額が異なります。
限度額の詳細については国税庁のホームページで最新情報を確認するとよいでしょう。
公共交通機関での通勤の場合
電車やバスなどの公共交通機関を利用して通勤する場合の非課税限度額は月15万円までと定められています。
ただし、非課税となるのは、1カ月分の通勤用定期乗車券の価格のうち、最も経済的かつ合理的な通勤経路・方法による正規運賃です。
グリーン車や特急などの割増料金は経済的合理性が認められないため、これらの料金分は全額課税対象となります。
また、同程度の通勤時間でより安価な経路が存在するにもかかわらず、より高額な定期券を選択した場合、その差額分は非課税限度額内であっても課税対象となることがあります。
公共交通機関で非課税となる通勤経路であるかは、実際の通勤距離や定期乗車券の運賃が合理的と判断できる経路を選ぶことが大切です。
交通用具での通勤の場合
マイカーや自転車による通勤手当の非課税限度額は、片道の通勤距離によって細かく定められています。
自動車と自転車のいずれの場合も、非課税となる限度額は同額で、片道2km未満の場合は全額が課税対象になります。片道2km以上の場合は、距離区分によって非課税限度額が定められています。
交通用具の非課税限度額については「マイカー通勤者の通勤交通費はどう考えればいい?計算方法のあれこれ」で詳しく触れていますので、そちらもご参照下さい。
たとえば、片道5kmの通勤では月額4,200円までが非課税となり、それを超える部分は所得税の課税対象となります。
通勤距離が長くなるほど非課税で認められる手当の金額も増えるため、正確な自宅から勤務先までの距離計測が必要になってきます。
企業はこの非課税枠を基に通勤手当を設定し、上限を超えた場合は超過分が課税されることに注意しなければいけません。
公共交通機関と交通用具の併用で通勤する場合
公共交通機関と自動車や自転車などの交通用具を併用して通勤する場合、非課税と認められる通勤手当の限度額は、利用している公共交通機関の1ヶ月分の定期券運賃と、自動車や自転車の通勤区間の片道距離に対する非課税限度額の合計で計算されます。
さらに、この合計額は1ヶ月あたり15万円を上限としています。
例えば自動車区間の非課税限度額が月10,000円、電車の定期代が月7,100円の場合、合計で17,100円となるので、15万円の上限を大きく下回っているため全額非課税の対象となります。
通勤手当が課税となる事例
通勤手当が所得税の課税対象と判断される事例についていくつか見ていきましょう。
徒歩通勤
企業によっては徒歩で通勤している従業員に対して、通勤手当を支給する場合もあります。
通勤手当の支給自体は企業ごとに自由に決めることができるのですが、徒歩通勤の場合の手当は所得税の非課税要件を満たさないため、課税対象となります。
理由としては、公共交通機関や自動車で通勤する場合と異なり、徒歩通勤では通勤に必要な経費が発生しないためです。
つまり、移動距離がどれだけ長くても費用がかからないため、支給された手当は非課税と認められず、全額が所得税対象となります。
通勤手当の1か月あたりの支給額が非課税限度額を越えている
国税庁が定めている通勤手当の非課税限度額の上限を超える額が支給された場合は、超過分が所得税の課税対象となります。
たとえば、公共交通機関で通勤している場合、会社から月16万円の通勤手当を支給されていれば15万円までが非課税となり、超えた1万円については所得税が課されます。
また、自動車や自転車など交通用具による通勤の場合も、距離に応じた非課税限度額を上回る部分は同様に課税対象となります。
その他の全額課税になる事例
通勤手当が全額課税となるケースですが、非合理的な通勤経路の利用、経済的とは認められない通勤手段の選択の場合、全額課税に該当します。
グリーン車利用など普通運賃を超えた費用分が支給される場合は、普通運賃との差額が課税対象です。
また、通勤手当としての支給目的以外の用途に使用される場合や、企業の規定に反して支給されている場合も課税になります。
Arvoで通勤管理を
今すぐ効率化
通勤手当の所得税への影響
通勤手当は、非課税範囲内で支給される場合、所得税の対象になりません。
しかし、非課税上限を超えた金額は課税対象となり、給与所得として扱われます。
この超過分は毎月の給与と合算され、所得税の計算に反映され、住民税の計算基礎にも含まれます。
通勤手当が所得としてどのように影響しているかは、給与明細で課税状況を確認するとよいでしょう。
また、確定申告の際にも、通勤手当の所得税課税の扱いを適切に申告することが求められます。
通勤手当の社会保険への影響
通勤手当は所得税以外にも、毎月の給与から天引きされる健康保険・介護保険・厚生年金保険・雇用保険といった社会保険料の計算へも直接影響します。
社会保険料の基礎となる標準報酬月額には、通勤手当が全額含まれます。
通勤手当の額が増えた場合、たとえ所得税や住民税の非課税限度額内で支給されている場合でも、社会保険料は増加する可能性があります。
社会保険料の算出基準は所得税や住民税とは異なり、非課税かどうかを問わず通勤手当全額が対象となるためです。
通勤手当の増減が社会保険料にどのような影響を及ぼすのかを理解し、正しく管理していきましょう。
まとめ|通勤手当の課税のルール
通勤手当は、国が定めた非課税限度額の範囲内であれば、所得税や住民税のいずれも課税されずに受け取ることができます。
しかし、非課税限度額を超えて支給された通勤手当については、その超過分が所得とみなされ課税対象になります。また、通勤手当の非課税適用には、通勤手段・通勤距離・支給額が合理的かつ経済的であるかも判断基準になります。
また、社会保険料の計算では通勤手当を全額含めるなど、所得税や住民税と社会保険料の取り扱いは異なる点にも注意が必要です。
これらの通勤手当の課税ルールをしっかり理解し、適切に管理していくとよいでしょう。
合理的かつ経済的な通勤経路を決定するには通勤管理サービスをご利用いただくことが有効です。
「通勤管理Arvo」には、規定にあった経路を自動で判断したり、公共交通機関の定期金額、片道金額、所要時間など任意の項目で並び替え表示する機能があり、効率的に通勤経路を決定できます。
「通勤管理Arvo」にご興味がありましたらお問い合わせください。
お問い合わせはこちらから
資料ダウンロードはこちらから
Arvoで通勤管理を
今すぐ効率化