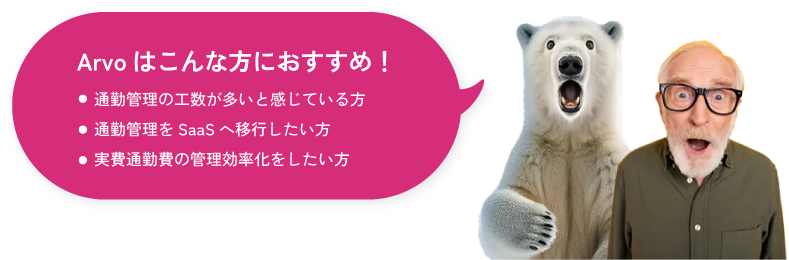育児休業給付金の計算に通勤手当は含まれる?|支給ルールや注意点を解説
育児休業給付金、通称「育休手当」の制度は、育児休業中の労働者の生活を経済的に支え、
安心して育児に取り組める環境を整備することを目的としています。
給与が支給されない休業期間中の経済的な不安を軽減することで、子育てに専念し、その後のスムーズな職場復帰を支援する重要な役割を担っています。
Arvoで通勤管理を
今すぐ効率化
育児休業給付金の計算基礎に通勤手当は含まれる
育児休業給付金の支給額を算出する際の基礎となる「休業開始時賃金日額」には、原則として通勤手当が含まれます。
この賃金日額は、育児休業を開始する直前6か月間に支払われた給与の総額を180日で割って計算されます。
給与総額には、基本給のほか、残業手当や住宅手当、そして通勤手当といった、毎月決まって支払われる各種手当も含まれるのが一般的です。
そのため、通勤手当の金額が高いほど、休業開始時賃金日額も高くなり、結果的に受け取れる育児休業給付金の額も増えることになります。
ただし、賞与など臨時的に支払われる賃金は計算の対象外になります。
そもそも育児休業給付金とは?制度の概要を解説
育児休業給付金、いわゆる「育休手当」とは、雇用保険の被保険者が育児のために会社を休業する際に、国から支給される給付金のことです。
育児休業中は会社からの給与が支払われないケースが多いため、その間の従業員の生活を支え、育児に専念できる環境を整えることを目的としています。
この制度により、労働者は経済的な不安を軽減しながら安心して子育てのための時間を確保し、その後のスムーズな職場復帰を目指すことが可能になります。
育児休業給付金がもらえる人の具体的な条件
育児休業給付金を受給するには、いくつかの条件を満たす必要があります。
まず、雇用保険に加入していることが前提です。
その上で、育児休業を開始する前の2年間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12か月以上あることが求められます。
次に、育児休業期間中の各1か月ごとに、休業開始前の1か月の賃金の8割以上の賃金が支払われていないことも条件の一つです。
さらに、休業期間中の就業日数が、各支給単位期間において10日以下である必要もあります。
有期契約労働者の場合は、子が1歳6か月に達する日までに労働契約が満了しないことも要件となります。
育児休業給付金の支給はいつからいつまで?
育児休業給付金の支給対象期間は、原則として子どもが1歳になる日の前日まで(1歳の誕生日の前々日)です。
また、1歳になる前に職場復帰した場合は、復帰日の前日までになります。
ただし、特定の条件下では期間を延長できます。
例えば、保育所への入所を希望しているにもかかわらず入所できない場合などは、最長で子どもが2歳になるまで延長が可能です。
延長申請には、以下の3つの書類が必要です。
・入所保留通知書
・育児休業給付金士空対象期間延長事由認定申告書
・保育所などへの申込書の写し
また、「パパ・ママ育休プラス」という制度を利用すると、両親がともに育児休業を取得する場合、
子どもが1歳2か月になるまで支育児休業を取得することもできます。
ただし、両親ともに1歳2か月まで期間延長ができるわけではなく、あとから育休を取得した方が1歳2カ月になるまで育休を取得することができる、という仕組みです。
【計算例】育児休業給付金でいくらもらえるかシミュレーション
育児休業給付金の支給額は、休業開始時の賃金を基に計算されます。
まず、育休開始前6か月の賃金総額を180で割り「休業開始時賃金日額」を算出します。
この日額に支給日数を掛けたものが「賃金月額」です。
この賃金月額に給付率を適用して支給額が決定します。
支給額は、育休開始から180日目までは「賃金月額×67%」、181日目以降は「賃金月額×50%」となります。
例えば、休業前の月収(通勤手当などを含む)が30万円だった場合、最初の6か月間は月額約20万1,000円(30万円×67%)、それ以降は月額約15万円(30万円×50%)が支給される計算です。
また、支給額には上限と下限が設定されています。
出生後休業支援給付金で給付率が上乗せになる
2025年4月1日から、「出生後休業支援給付金」という新たな給付金制度が始まりました。
この制度は、出産直後の育児休業を強力に支援することを目的としており、従来の育児休業給付金に最大28日間、休業前賃金の約13%相当額が上乗せして支給されます。
この給付金と育児休業給付金と合わせることで、休業開始前の賃金の約80%が給付されることになり、社会保険料の免除と非課税措置を考慮すると、実質的に手取り収入の約10割が補填される計算になります。
ただし、この給付金を受けるにはいくつかの要件があります。
まず、雇用保険の被保険者であることに加え、被保険者が対象期間に、同一の子について出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得していることが必要です。
さらに、配偶者も所定の期間内に通算して14日以上の育児休業を取得していること、または配偶者の育児休業を要件としない場合に該当していることも条件となります。
Arvoで通勤管理を
今すぐ効率化
育児休業中の通勤手当は支給される?会社の規定を確認しよう
育児休業給付金の計算基礎には通勤手当が含まれますが、では実際に育児休業を取得している期間中に会社から通勤手当が支払われるかどうかについては、 法律で一律に定められているわけではなく、
各企業の就業規則や賃金規程によって決定されることになります。
通勤手当の扱いは会社の就業規則で定められている
育児休業中の通勤手当を支給するか否かは、それぞれの会社の就業規則や賃金規程に委ねられています。
多くの企業では、育児休業や介護休業といった長期の休業期間中は、通勤の実態がないため通勤手当を支給しないと定めています。
もし定期券を購入している場合は、休業に入る前に払い戻し手続きを行うよう指示されるのが一般的でしょう。
休業の申し出をする際には、通勤手当の扱いや定期券の払い戻しについて、必ず会社の担当部署に確認しておくことが大切です。
実費精算が一般的な通勤手当の取り扱い
通勤手当は、従業員が自宅から会社まで通勤するために実際にかかる費用を補填する、いわゆる「実費弁償」の性質を持つ手当で、支給するための規定は会社ごとに制定されています。
そのため、出勤という事実が発生しない育児休業期間中は、支給の根拠がなくなるため支払われない場合もあり、その場合、もし休業中に研修などで一時的に出社する必要が生じた場合は、その都度、
交通費として実費が精算されることが多いと思います。
また、育児休業期間中でも通勤手当が月額支給されるケースもあり、 会社によって規定はことなるのが通常ですので、 最終的には自社の就業規則がどうなっているかを確認することが最も確実です。
【要注意】育休中に通勤手当をもらうと給付金が減るケース
万が一、育児休業期間中に会社から通勤手当や賃金が支払われた場合、受け取れる育児休業給付金の額が減額されたり、全額不支給になったりする可能性があります。
これは、育児休業給付金が休業によって低下する収入を補うための制度であるためです。
給付金が減額または不支給となる賃金額のボーダーライン
育児休業中に会社から賃金が支払われると、育児休業給付金が調整されます。
具体的には、支払われた賃金額が休業開始前の賃金月額の13%を超えると、給付金は減額され始めます。
そして、支払われた賃金額が休業開始前の賃金月額の80%以上に達すると、その支給単位期間の給付金は全額不支給となります。
この計算の対象となる「賃金」には、通勤手当だけでなく、住宅手当や扶養手当など、名称を問わず会社から支払われるすべての金銭が含まれます。
育休中の社会保険料は支払いが免除される
育児休業期間中は、経済的な負担を軽減するための制度として、健康保険料や厚生年金保険料といった社会保険料の支払いが免除されます。
この免除は、被保険者本人負担分だけでなく、会社が負担する事業主負担分も対象となります。
免除を受けるために、休業に入る前に事業主(会社)を通じて「育児休業等取得者申出書」を年金事務所または健康保険組合に提出します。
この手続きによって、保険料の支払いが免除されている期間も、将来の年金額の計算においては保険料を納付したものとして扱われることで、被保険者にとって不利益は生じない仕組みになっています。
育児休業給付金を受け取るための申請手順
育児休業給付金を受け取るための申請は、原則として勤務先の会社を通じて行います。
まず、従業員は育児休業を開始する1か月前までに会社へ休業の申し出をします。
その後、会社から「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」などの必要書類を渡されるので、記入して会社に提出します。
会社は、提出された書類と賃金台帳や出勤簿などを合わせて、事業所の所在地を管轄するハローワークに提出します。
初回の申請後は、原則として2か月に1度、会社経由で支給申請を行う流れとなります。
まとめ
育児休業給付金は、育児休業中の生活を経済的に支援する重要な制度です。
その計算基礎については通勤手当も含まれます。
育児休業期間中に会社から通勤手当が支給されるかどうかは、各企業の就業規則によって異なりますので、事前に確認をしましょう。
ただし育児休業中に会社から一定額以上の賃金が支払われた場合は、育児休業給付金が減額されたり、不支給になったりする可能性があり、この中には通勤手当も含まれます。
支給額のボーダーラインは、休業開始前の賃金月額の13%(減額開始)および80%(不支給)になります。
また、2025年4月1日から導入された「出生後休業支援給付金」を利用することで、従来の育休給付金と合わせることで実質の手取り額は、休業前賃金の約10割が受け取れることになります。
これらの制度を理解し、適切に活用することで安心して育児に専念することができ、スムーズな職場復帰を目指せるでしょう。
育休手当にも影響する、通勤手当額を正確に管理するには通勤管理サービスの利用も有効です。
「通勤管理Arvo」にご興味がありましたらお問い合わせください。
お問い合わせはこちらから
資料ダウンロードはこちらから
Arvoで通勤管理を
今すぐ効率化