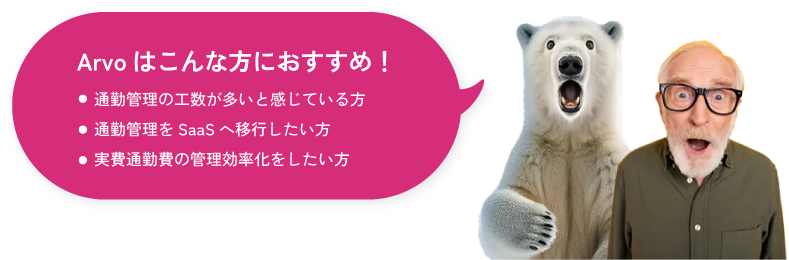運賃改定時の業務を効率よく行うには?|通勤管理サービスの活用について
相次ぐ鉄道会社の運賃改定は、企業の通勤費管理業務に大きな影響を与えています。
従業員の通勤手当を正確に計算し直す作業は、担当者にとって大きな負担になります。
この記事では、運賃改定がなぜ交通費管理業務を煩雑にするのか、手作業によるリスクを明らかにし、 業務効率化を実現する通勤管理サービスの活用法と、最適なサービスを選ぶためのポイントについて説明します。
Arvoで通勤管理を
今すぐ効率化
運賃改定によって通勤管理の業務はなぜ煩雑になるのか?
近年、鉄道各社の運賃改定は相次いで実施されており、特に新年度が始まる4月頃に集中する傾向があります。
人事労務や総務の担当者はその度毎に、全従業員の通勤費を新しい運賃体系に基づいて再計算し、適切に支給し直す必要があります。
この作業には多くの手作業が発生し、通勤管理業務が大幅に煩雑化します。
全従業員の通勤経路と定期代を再計算する必要がある
運賃改定が行われると、企業は全従業員の通勤経路とそれにかかる費用を、改定後の新運賃に照らし合わせて一から再計算しなければなりません。
従業員一人ひとりが利用する路線や区間を確認し、新しい通勤定期代を算出する作業は、従業員数が多い企業ほど膨大な時間を要します。
特に、複数の交通機関を乗り継ぐ複雑な経路を持つ従業員の場合、計算はさらに煩雑になります。
この再計算作業は給与支給のタイミングに間に合わせる必要があり、担当者には限られた期限内での正確性とスピードの両方が求められ、大きなプレッシャーがかかります。
申請内容が最新の運賃に基づいているか目視で確認
新規入社者や転居した従業員からの通勤費申請があった際には、その内容が最新の運賃体系に基づいているかを担当者が一つひとつ目視で確認する必要があります。
担当者はWebの乗り換え案内サイトなどを利用して、申請された経路が合理的であるか、金額に誤りがないかをチェックしていきます。
この確認作業は非常に手間がかかり、特に運賃改定の直後は申請数も集中することから、担当者の業務負担を著しく増加させます。
運賃改定対象の通勤経路を持つ社員のピックアップ
運賃改定の際は、企業は全従業員の通勤経路を調査し、どの従業員の通勤費が改定の対象となるかを特定する作業が発生します。
これは非常に手間のかかる作業で、特に複数の交通機関を乗り継ぐ従業員が多い場合、確認にはより時間を要することになります。
例えば、JR線の運賃が改定された場合、JR線を利用している従業員を抽出し、その従業員の通勤経路に含まれるJR線の区間や運賃を確認しなければなりません。
私鉄や地下鉄、バスなど、複数の交通機関を組み合わせた経路の場合、それぞれの交通機関の運賃改定情報を個別に把握し、それが従業員の通勤経路にどのような影響を与えるかを判断する必要があります。
また、乗り入れ割引などの有無や金額の確認も合わせて確認していく必要があります。
この確認作業を手作業で行う場合、従業員一人ひとりの定期券情報や交通経路を個別に確認し、改定対象となる従業員をリストアップするという膨大な作業が発生します。
この作業には高い集中力と正確性が求められ、少しでも見落としがあると、不適切な通勤手当の支給につながるリスクがあります。
給与計算システムへの手作業によるデータ入力
運賃改定に伴い再計算した、全従業員の新しい通勤手当のデータは、最終的に給与計算システムへ反映させる必要があります。
Excelなどで管理している通勤費リストから、給与計算システムへ一人ずつ金額を転記していく作業は、非常に時間がかかり、入力ミスが発生するリスクも高まります。
特に労務の担当者は、毎月の給与計算というミスが許されない重要な業務を担っており、この手作業によるデータ入力は、業務の正確性を脅かすだけでなく、精神的な負担も大きい作業です。
Arvoで通勤管理を
今すぐ効率化
Excelや手作業による通勤費管理が抱える3つのリスク
運賃改定時のような正確な計算処理を求められる作業をExcelや手作業で行っている場合、様々なリスク発生が懸念されます。
単純な計算ミスから、担当者の過度な業務負担、さらには法改正への対応遅れまで、その影響は多岐にわたります。
ここでは、旧来の管理方法が内包する3つの具体的なリスクについて解説します。
ヒューマンエラーによる支給額の間違い
手作業による通勤費管理で最も懸念されるのが、ヒューマンエラーによる支給額の間違いです。
運賃改定時の全従業員の定期代再計算や、給与システムへのデータ入力といった一連の作業は、手動で行う限り入力ミスや計算ミスを完全になくすことは困難です。
もし誤って過払いしてしまった場合、企業にとっては不要なコスト増となり、逆に過少支給であった場合は、従業員との信頼関係を損なう原因にもなりかねませんし、 このようなミスは、後から修正するための追加業務も発生させ、結果的にさらなる業務負担へとつながります。
担当者の業務時間が大幅に増加する
運賃改定が発生すると、通勤費管理を担当する部署の業務時間は大幅に増加します。
全従業員の通勤経路を確認し、新しい運賃で再計算し、その結果を給与システムに入力するという一連の作業を、限られた期間内で対応することを求められます。
この業務負担の増加は、担当者の負荷増加を招くだけでなく、本来注力すべきコア業務への時間を圧迫し、組織全体の生産性低下にも影響する可能性があります。
複雑な運賃体系や各種法改正への対応が困難
近年の交通機関における運賃体系は、ICカード利用と切符購入での料金差や、乗り入れ割引の適用などによって、ますます複雑化してきています。
手作業でこれらの条件をすべて考慮し、最も経済的な経路となる通勤手当を決定するのは非常に困難です。
また、通勤手当の非課税限度額の引き上げなど、関連する法改正が行われた際にも、正確な対応が求められます。
Excelや手作業による管理では、これらの複雑なルールや制度変更への追従に追われることになり、さらに業務負荷が高まります。
Arvoで通勤管理を
今すぐ効率化
通勤管理サービスで運賃改定時の業務負担を大幅に削減
Excelや手作業による管理が抱えるリスクを回避し、運賃改定時の業務負担を劇的に軽減する有効な手段として考えられるのが、通勤管理サービスの導入です。
これらのサービスは、運賃改定情報の自動反映や最適な経路の自動算出、給与システムとの連携など、通勤費管理に特化した多彩な機能を備えています。
システムを活用することで、手作業を大幅に削減し、業務の正確性と効率を飛躍的に向上させることが可能です。
運賃改定情報を自動で反映し、再計算の手間をなくす
通勤管理サービスの最大の利点の一つは、各交通機関の運賃改定情報をシステムが自動で取得し、反映する機能です。
これにより、担当者が自ら情報を収集し、全従業員の通勤費を一人ひとり手作業で再計算する必要がなくなります。
システムが最新の運賃データに基づいて自動的に通勤手当を再計算してくれるため、運賃改定に伴う膨大な作業から解放されます。
この機能により、計算ミスというヒューマンエラーのリスクを根本から排除できるだけでなく、担当者は大幅に時間を削減し、他の重要な業務に集中できるようになります。
最適な通勤経路と運賃をシステムが自動で算出
多くの通勤管理サービスは、出発地と目的地を入力するだけで、最も経済的かつ合理的な通勤経路を自動で算出する機能が搭載されています。
この機能を利用することで、単に最短時間や最安値の経路を提示するだけでなく「定期代が最も安い経路」など、企業の規定に合わせた条件での検索が可能になります。
従業員が申請した経路が最適かどうかをシステムが自動で判定するので、通勤管理業務の担当者が一件ずつ目視で確認する手間が省けます。
これにより、通勤手当額も最適に保ち、会社全体の交通費を適正化することにも寄与します。
給与計算システムとの連携でデータ入力が不要に
多くの通勤管理サービスは、主要な給与計算システムとのデータ連携機能を備えています。
これにより、通勤管理サービスで確定した全従業員の通勤手当データをボタン一つで出力し、給与計算システムに反映させることができます。
従来、手作業で行っていたデータ転記の工程がなくなり、入力ミスが発生するリスクを削減できます。 給与計算はミスが許されない業務ですので、給与支給業務全体の正確性とスピードを向上させます。
申請から承認までのプロセスを電子化し迅速化
通勤管理サービスを導入することで、通勤費に関する各種申請から上長による承認、担当部署での確認といった一連のワークフローをすべて電子化することができます。
紙の申請書を回覧する必要がなくなるほか、誰がいつ申請し、誰が承認したかといった記録がシステム上にすべて残るので、内部統制、監査対応の効率化にもつながります。
Arvoで通勤管理を
今すぐ効率化
自社に合った通勤管理サービスを選ぶための比較ポイント
通勤管理サービスの導入効果を最大化するためには、自社の運用方法や既存システムとの相性を考慮して、最適なサービスを選ぶことが大切です。 各サービスが提供する機能や料金体系は様々で、単に多機能なものを選べば良いというわけではありません。
自社の通勤規定にマッチしているか
通勤管理サービスを選ぶ際は、自社の通勤規定にサービスが対応できているかを最優先で確認します。 企業によっては、「特急料金は支給しない」「特定の交通手段のみを認める」「経路は自宅から会社までの最短距離を推奨する」といった独自の規定を設けている場合があります。
多くのサービスは、汎用性のある通勤経路検索機能を提供しており、複雑な規定にどこまで対応できるのかは各サービスによってまちまちです。
例えば、新幹線の通勤を許可している企業では、新幹線を利用する経路検索や運賃算出ができるかがサービスの選定基準となります。
また、複数の交通機関を組み合わせた経路検索の際に、自社の規定に沿った優先順位(例:電車優先、バス優先など)を設定できる機能を持つサービスもあります。
導入前に自社の通勤規定と照らし合わせて対応できる機能が備わっているかや、業務運用に沿った機能を有しているかをしっかり見極めて、導入後のミスマッチなくスムーズな運用へと繋けてください。
既存の給与システムや勤怠管理システムと連携できるか
通勤管理サービスを選ぶ上で、給与計算システムや勤怠管理システムとスムーズに連携できるかどうかも重要なポイントの一つになります。
データ連携ができない場合、結局は手作業でのデータ移行が発生し業務効率化の効果が半減してしまいますので、 導入を検討しているサービスが、自社のシステムに対応しているか、CSVファイルなどで柔軟なデータ連携が可能かなどを事前に必ず確認する必要があります。
シームレスな連携が実現できれば、データ入力の手間を完全に排除し、一貫性のある効率的な業務フローを構築できます。
導入時や運用開始後のサポート体制は手厚いか
新しいシステムの導入には、初期設定や操作方法の習熟など、不明点や問題が発生しやすいものです。 そのため、導入時の設定サポートや、運用開始後の問い合わせに迅速かつ丁寧に対応してくれるサポート体制が整っているかどうかも重要な確認ポイントになります。
電話やメール、チャットなど、どのような問い合わせ方法があるか、対応時間はどうなっているかなどをぜひご確認ください。
まとめ
通勤費管理は、企業にとって不可欠な業務ですが、鉄道会社の運賃改定が頻繁に行われる昨今、
その業務負担は増大しています。
手作業での対応は、計算ミスや入力ミスといったヒューマンエラーのリスクを高めるだけでなく、担当者の業務時間を大幅に増加させ、本来注力すべきコア業務に支障をきたす可能性もあります。
さらに、複雑な運賃体系や各種法改正への対応も大きな課題です。
このような課題を解決し、通勤管理業務の効率化と正確性向上を実現するためには、通勤管理サービスの導入が非常に有効です。
通勤管理サービスは、運賃改定情報の自動反映や最適な通勤経路・運賃の自動算出、そして給与計算システムとの連携など、通勤費管理に特化した多様な機能を備えています。
これにより、手作業による再計算やデータ入力の手間が大幅に削減され、ヒューマンエラーのリスクも低減できます。
通勤管理サービスを選ぶ際には自社の規定とのマッチ度のほか、給与システムなどとの連携、サポート体制などをご確認いただき、最適なサービスを選定してください。
「通勤管理Arvo」にご興味がありましたらお問い合わせください。
お問い合わせはこちらから
資料ダウンロードはこちらから
Arvoで通勤管理を
今すぐ効率化