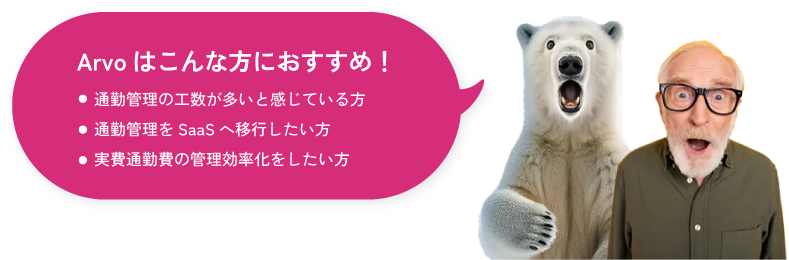「同一労働同一賃金」と通勤管理の関係について|押さえておくポイント
同一労働同一賃金の導入により、パートやアルバイトといった非正規雇用の従業員に対しても、原則として通勤手当の支給が求められるようになりました。
本記事では、同一労働同一賃金の基本から、通勤手当の具体的な判断基準、そして企業の管理上の課題と対応策について詳しく解説します。
Arvoで通勤管理を
今すぐ効率化
同一労働同一賃金とは?基本を知る
同一労働同一賃金とは、同じ企業内で働く正社員とパートタイマーや有期雇用労働者、派遣社員といった非正規雇用労働者との間で、
雇用形態を理由とする不合理な待遇差を設けることを禁止するルールのことです。
これは、大企業では2020年4月、中小企業では2021年4月から施行された
「パートタイム・有期雇用労働法」
によって定められました。
基本給や賞与だけでなく、各種手当や福利厚生などあらゆる待遇が対象となり、職務内容や責任の範囲、配置の変更範囲などが同じであれば、原則として同一の待遇を確保する必要があります。
同一労働同一賃金によって通勤手当の扱いはどう変わるのか
同一労働同一賃金の原則は、通勤手当の取り扱いにも適用されます。
通勤手当は通勤にかかる実費を補填するという性質を持ち、職務内容が同じ正社員に支給されている場合はパートやアルバイト、派遣社員といった非正規雇用の従業員に対しても、原則として同様に支給しなければなりません。
雇用形態が違うという理由だけで通勤手当を支給しなかったり支給額に差を設けたりすることは、不合理な待遇差と見なされる可能性があります。
派遣・パート・アルバイトにも通勤手当の支給が必要になる
パートタイム・有期雇用労働法の施行により、派遣社員やパートタイマー、アルバイトなど、いわゆる非正規雇用の従業員に対しても、通勤手当の支給が原則として必要になりました。
従来は、通勤手当分を考慮して時給を高めに設定するといった対応も見られましたが、この法律の趣旨に基づけば、通勤手当は基本給とは別に、通勤にかかる実費を補填するものとして支給することが求められます。
もし正社員と非正規社員の間で通勤手当の支給に差を設ける場合は、その違いが職務内容や勤務形態の違いなど、客観的かつ合理的な理由に基づくものであることを企業側が説明できなければなりません。
不合理な待遇差はNG!事例から見る判断基準
通勤手当における不合理な待遇差の判断は、厚生労働省が示すガイドラインに基づき、個別の事情を考慮して行われます。
原則として、通勤にかかる費用を補填するという手当の性質上、正社員(無期雇用フルタイム労働者)に支給しているにもかかわらず、パートやアルバイトといった非正規社員に支給しないことは、不合理な待遇差と判断される可能性が極めて高いです。
判断基準となるのは、職務内容、当該職務内容及び配置の変更の範囲、その他の事情です。
通勤という行為自体は雇用形態によって変わるものではないため、雇用形態のみを理由とした待遇差は認められにくい事情となります。
Arvoで通勤管理を
今すぐ効率化
要注意!通勤手当で不合理な格差と見なされる具体例
同一労働同一賃金の原則に違反しないために、どのようなケースが「不合理な待遇差」と判断されるのかを具体的に把握しておくことも大切です。
特に通勤手当においては、意図せず不合理な格差を生じさせてしまう可能性があります。
ここではどのような規定が問題となり得るのか、企業が注意すべき具体的な事例を紹介します。 自社の規定と照らし合わせすための参考にしてください。
正社員と非正規社員で支給額の上限が異なるケース
通勤手当の支給額について、正社員と非正規社員とで異なる上限額を設定することは、不合理な待遇差と見なされる可能性があります。
例えば、「正社員の上限は月5万円まで、パートタイマーの上限は月1万円まで」といった規定は、雇用形態のみを理由とした格差と判断される場合があります。
通勤にかかる費用は、従業員の居住地と勤務地の距離によって決まるものであり、雇用形態とは直接的な関係がないからです。
通勤手当が通勤という事実に対して支給されるものである以上、その上限額に合理的な理由のない差を設けることをせず、全従業員に共通の基準を適用することが求められます。
実費に対する支給率に雇用形態で差を設けているケース
通勤にかかった実費に対する支給率を、雇用形態によって変えることも不合理な待遇差と判断されます。
具体的には「無期雇用の従業員には通勤費の実費を全額支給するが、有期雇用の従業員には8割のみ支給する」といったケースです。
通勤手当は、従業員の経済的負担を軽減するための福利厚生としての側面が強く、労働の対価である賃金とは性質が異なります。
そのため、通勤という同じ行為に対して、雇用形態を理由に支給率で差を設けることの合理性を説明するのは困難でしょう。
企業としては、全ての従業員に対して公平な支給率を適用し、不合理な格差が生じないよう注意を払う必要があります。
合理的な理由があれば通勤手当に差を設けることは可能
同一労働同一賃金は、あらゆる待遇差を禁止するものではなく、その差が客観的・合理的な理由に基づくものであれば合理的と判断されます。これは通勤手当についても同様です。
どのような理由であれば、交通費や通勤費の差が「合理的」と判断されるのか、具体的な例を見ていきましょう。
勤務日数や時間に応じて支給額を変える
勤務日数といった、実際の働き方の違いに基づいて通勤手当の支給額に差を設けることは、合理的な待遇差として認められます。
例えば、週5日フルタイムで勤務する従業員には1ヶ月分の通勤定期代を支給し、週2日勤務のパートタイマーには出勤日数に応じた往復運賃の実費を支給するという方法は合理的です。
この場合の差は、雇用形態の違いではなく、実際の通勤頻度の違いに基づいているため、問題とはなりません。
ただし、時給制のパートタイマーであっても、正社員とほぼ同じ日数・時間勤務している場合には、同様の通勤手当を支給する必要がある点に留意が必要です。
勤務実態に即した公平な支給基準を設けることが求められます。
Arvoで通勤管理を
今すぐ効率化
派遣社員への通勤手当の支給方法は2種類ある
派遣社員の待遇を決定する方式には「労使協定方式」と「派遣先均等・均衡方式」の2種類があり、通勤手当の支給方法についてもどちらの方式を採用するかによって異なります。
派遣元企業はいずれかの方式を選択し、それに基づいて派遣社員の通勤手当を含む待遇を決定する義務があります。
労使協定方式
労使協定方式とは、派遣元の会社が自社の労働者の過半数代表者と労使協定を締結し、その協定に基づいて派遣社員の待遇を決定する方式です。 多くの派遣会社で採用されています。
この方式における通勤手当は、厚生労働省の通達で定められた「一般の労働者の通勤手当に相当する額」以上を支給する必要があります。
具体的な支給方法としては、通勤にかかる実費を支給するか、または一般労働者の時間あたりの通勤手当額とされる金額を時給に加えて支給する方法のいずれかを選択します。
実費支給の場合は、最も経済的かつ合理的な経路に基づいて算出された金額を支払うことになります。
派遣元均等・均衡方式
派遣先均等・均衡方式は、派遣社員の待遇を、派遣先企業で同じ業務に従事している通常の労働者(正社員など)の待遇に合わせて決定する方式です。
この方式を採用する場合、通勤手当も派遣先の従業員の支給基準と均等または均衡な取り扱いをする必要があります。
つまり、派遣先の正社員に適用される通勤手当の規定に基づき、派遣社員にも同等の手当を支給することになります。
この方式を適用するため、派遣先企業が比較対象となる労働者の待遇情報(通勤手当の支給ルールや上限額など)を派遣元企業に提供することが法律で義務付けられています。
情報提供などの面で派遣先企業の協力が不可欠となるため、労使協定方式に比べて採用例は少ない傾向にあります。
企業が直面する通勤手当の管理における課題
同一労働同一賃金の適用により、パートやアルバイトへの通勤手当支給が広がり支給対象者が増し、通勤業務の管理対象とする範囲が広がったことで、人事・労務担当者の負担が増大しています。
支給対象者の増加による管理業務の煩雑化
これまで通勤手当の支給対象でなかったパートタイマーやアルバイトが新たに対象となったことで、管理すべき従業員の数が大幅に増加しました。
人事・労務担当者は、対象者一人ひとりの通勤経路の申請を受け付けその内容を確認し、最も経済的な経路であるかを検証した上で通勤経路の決定、支給額を算出しなければなりません。
特に勤務日数に応じた通勤手当を支給する場合はシフト制で勤務日数が変動するので、毎月出勤実績を確認して日割りの通勤交通費を計算する必要があり、手作業で管理することは多くの時間や労力を必要とします。
こうした業務量の増加は担当者の負担を重くするだけでなく、計算ミスや支給漏れといったヒューマンエラーの発生を高める要因にもなります。
申請された通勤経路の妥当性チェックに手間がかかる
従業員から申請された通勤経路が、会社規定に照らして最も経済的かつ合理的であるかを確認する作業というのは、時間と手間を必要とします。
対象者が増えれば、その負担はさらに大きくなります。 申請された経路が最短・最安でない場合、そのまま採用すると過大な通勤交通費を支給してしまうことにつながるため、妥当性のチェックは不可欠です。
しかし、全ての申請に対して一件ずつ検証するのは大変な時間がかかることも事実です。
また、従業員の転居による経路変更や公共交通機関の運賃改定なども定期的に反映させる必要があり、手作業での正確な情報管理を維持することは非常に負荷の高い業務になります。
まとめ
同一労働同一賃金の原則を定めたパートタイム・有期雇用労働法により、通勤手当においても雇用形態を理由とする不合理な待遇差は認められなくなりました。
企業は、正社員に通勤手当を支給している場合、パートやアルバイト、派遣社員といった非正規雇用の労働者にも、原則として同様の待遇を提供する必要があります。
ただし、勤務日数や転勤の有無といった職務内容の違いなど、客観的で合理的な理由があれば、支給内容に差を設けることは合理的と版出されます。
また、派遣社員については派遣元が採用する「労使協定方式」または「派遣先均等・均衡方式」のいずれかに基づいて通勤手当の支給対応が決定されることには、留意が必要です。
通勤管理の対象範囲が広がったことで、業務負荷はさらに増加しました。通勤管理サービスを利用することで、通勤経路の妥当性チェックや正確な通勤手当額の算出ができ、業務効率化が実現できるかもしれません。
「通勤管理Arvo」にご興味がありましたらお問い合わせください。
お問い合わせはこちらから
資料ダウンロードはこちらから
Arvoで通勤管理を
今すぐ効率化