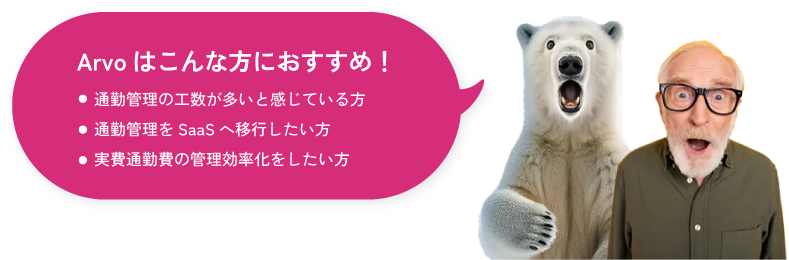雇用保険の計算について|通勤手当との関係も
雇用保険は、企業に所属している従業員は、一定の基準を満たす場合に必ず加入する必要があります。 雇用保険料の計算は、働く世代の生活を守るためにも重要な業務です。
この解説では、雇用保険料の計算方法の基本から、通勤手当が計算にどう影響するのか、雇用形態別の計算方法、そして計算における注意点まで、網羅的にご紹介します。
Arvoで通勤管理を
今すぐ効率化
雇用保険の基本を知る
雇用保険は、労働者が失業した場合や、育児・介護などで働くことが困難になった場合に、生活や雇用の安定を図るための公的な保険制度です。また、失業予防や雇用機会の増大、能力開発といった目的も担っています。
この制度を維持するための費用が雇用保険料は、事業主と労働者の双方が負担しています。
雇用保険料とは
雇用保険料は、労働者が失業した場合などに給付される失業手当や、育児休業給付金などの各種給付金の支払いに充てられます。
この雇用保険料は、被保険者の賃金総額に事業の種類ごとに定められた雇用保険料率を乗じて算出されます。
労働者負担分は給与から控除され、事業主負担分と合わせて事業主が国に納付します。
雇用保険の支払い義務者
雇用保険の保険料は、事業主と労働者の双方が負担します。
負担割合は事業の種類によって異なりますが、一般的に事業主の負担割合の方が労働者の負担割合よりも大きくなっています。
事業主は、雇用する労働者が雇用保険の加入条件を満たしている場合は、雇用形態に関わらず加入手続きを行い、毎月の給与から労働者負担分の雇用保険料を控除し、事業主負担分と合わせて納付する義務があります。
雇用保険料の計算方法
雇用保険料の計算は、対象となる賃金額に雇用保険料率を乗じて行われます。
計算時には、1円未満の端数処理についても規定があります。
計算に用いる賃金について
雇用保険料を計算する際に用いられる賃金は、労働の対償として事業主から労働者に支払われるすべてのものになります。
基本給はもちろんのこと、残業手当、家族手当、住宅手当など、名称にかかわらず労働の対価とみなされるものが対象に含まれます。
所得税においては非課税となる通勤手当も、雇用保険料の計算においては対象となる賃金に含めて計算する必要があります。
ただし、退職金や慶弔見舞金など、労働の対価とはみなされないものは対象になりません。
雇用保険料率の適用
雇用保険料率は、事業の種類によって異なります。
一般の事業、農林水産・清酒製造の事業、建設の事業の3つに区分されており、それぞれの事業で労働者負担分と事業主負担分の雇用保険料率が定められています。
これらの料率は景気や雇用情勢によって変動することがあるため、最新の雇用保険料率を確認して計算を行うことが求められます。
具体的な計算式
雇用保険料は
「対象となる賃金総額×雇用保険料率」
という計算式で算出されます。
労働者負担分の雇用保険料は、労働者に支払われる賃金総額に労働者負担分の雇用保険料率を乗じて計算します。
同様に、事業主負担分の雇用保険料は、賃金総額に事業主負担分の雇用保険料率を乗じて計算します。
計算で発生した端数の処理
雇用保険料を計算した結果、1円未満の端数が発生した場合は、原則として
「50銭以下切り捨て、50銭1厘以上切り上げ」
で処理します。
これは、労働者の給与から雇用保険料を源泉徴収する場合に適用されるルールです。
ただし、労働者が事業主に現金で雇用保険料を支払う場合は、
「端数が50銭未満は切り捨て、50銭以上の場合は切り上げ」
となります。
また、労使間で慣習的な端数処理の特約がある場合は、その特約に従うことも認められています。
Arvoで通勤管理を
今すぐ効率化
賃金における通勤手当の扱い
通勤手当は、雇用保険料の計算において、その扱いが所得税の場合と異なります。
所得税法上では一定額まで非課税扱いとなる通勤手当ですが、雇用保険法上では労働の対償とみなされ、雇用保険料の算定基礎に含まれます。
雇用保険料の計算における通勤手当
雇用保険料の計算において、通勤交通費は賃金総額に含めます。
所得税法上は非課税となる非課税通勤費であっても、雇用保険においては賃金として扱い、保険料の計算対象となります。
したがって、給与計算を行う際には、所得税と雇用保険で通勤手当の扱いが異なる点に注意し、それぞれ正しく計算に含める必要があります。
非課税通勤費について
非課税通勤費とは、所得税法によって定められた、所得税が課税されない通勤手当の上限額のことです。
公共交通機関を利用している場合は1ヶ月あたり15万円までが非課税となるなど、通勤方法によって上限額が異なります。 この非課税限度額を超える部分の通勤手当は、所得税の課税対象となります。
しかし、雇用保険料の計算においては、非課税通勤費かどうかにかかわらず、労働者に支払われる通勤手当の全額が計算の対象となります。
雇用形態別の雇用保険料計算
雇用保険は、原則として雇用形態に関わらず一定の要件を満たす労働者に適用されます。
したがって、月給者、日給者、時給者、パートタイム労働者など、様々な雇用形態の労働者に対して雇用保険料の計算が必要となります。
計算方法は基本的に共通していますが、それぞれの雇用形態における賃金の支払われ方を考慮する必要があります。
月給者の計算
月給者の雇用保険料は、毎月固定で支払われる基本給に加え、残業手当や各種手当、そして通勤手当など、その月に支払われる賃金総額を基に計算します。
計算式は「賃金総額×雇用保険料率」となり、他の雇用形態と同様です。
毎月の給与額が比較的安定していることが特徴です。
日給者の計算
日給者の雇用保険料は、労働日数に応じて支払われる日当の合計額に、その他の手当や通勤手当を含めたその月の賃金総額を基に計算します。
労働日数によって月々の賃金総額が変動するため、毎月正確な賃金総額を把握し、計算を行います。
時給者の計算
時給者の雇用保険料は、働いた時間数に応じた時給の合計額に、手当や通勤手当を含めたその月の賃金総額を基に計算します。
労働時間によって月々の賃金総額が変動するため、日給者と同様に毎月正確な賃金総額を把握して対応します。
パートタイム労働者の計算
パートタイム労働者も、一定の要件(週の所定労働時間、雇用見込み期間など)を満たす場合は雇用保険の適用対象となります。
計算方法は、時給者と同様に働いた時間数に応じた賃金や各種手当、通勤手当を含めたその月の賃金総額を基に行います。
短時間勤務の場合でも、雇用保険の加入要件を満たしていれば適切に計算し、保険料の納付が求められます。
Arvoで通勤管理を
今すぐ効率化
雇用保険料に関する注意点
雇用保険料の計算や納付においては、いくつかの注意点があります。 特に賞与からの保険料控除や、賃金変動があった場合の影響について理解しておくことが大切です。
賞与からの保険料控除
雇用保険料は、毎月の給与だけでなく、賞与からも控除する必要があります。
賞与に対する雇用保険料の計算方法も、通常の給与の場合と同様に「賞与額×雇用保険料率」となります。
労働の対価として支払われる一時金である賞与も、雇用保険料の算定基礎に含まれるため、賞与を支給する際には忘れずに雇用保険料を計算、控除することになります。
退職後に支払われる賞与であっても、退職前の労働に対する対価であれば雇用保険料の控除対象となります。
賃金変動の影響
雇用保険料は、対象となる賃金総額に雇用保険料率を乗じて計算されるため、残業手当の増減などにより月々の賃金総額が変動すると、それに伴って雇用保険料も変動します。
健康保険や厚生年金保険のように標準報酬月額を基に年間を通じて保険料が固定される社会保険とは異なり、雇用保険料は原則として毎月の賃金支払額に基づいて計算し直す必要があります。
雇用保険料に関するよくある質問
支払い義務者や保険料率の確認方法など、いくつかの疑問点について解説します。
誰が雇用保険料を支払うのか
雇用保険料は、労働者と事業主の双方が負担します。
事業主は、雇用する労働者の賃金から労働者負担分の雇用保険料を控除し、事業主負担分と合わせて国に納付する義務を負います。
雇用保険料率を確認する方法
雇用保険料率は、厚生労働省のウェブサイトなどで確認することができます。
事業の種類ごとに料率が定められており、年度によって改定される場合があるため、最新の情報を参照するようにしましょう。 また、ハローワークに問い合わせることでも確認できます。
まとめ
雇用保険料の計算において、通勤手当は所得税とは異なり、課税・非課税に関わらず賃金総額に含める必要があります。
雇用保険料は、対象となる賃金総額に雇用保険料率を乗じて算出され、月給者、日給者、時給者、パートタイム労働者など、雇用形態に関わらず計算が必要です。
賞与からも保険料は控除され、賃金変動に応じて保険料額も変動します。
正確な給与計算と雇用保険料の納付を行うため、最新の雇用保険料率を確認し、端数処理にも留意して適切な手続きを行いましょう。
雇用保険にもかかわる通勤手当を正確に管理するため、通勤管理サービスを利用することも業務効率化につながります。
「通勤管理Arvo」にご興味がありましたらお問い合わせください。
お問い合わせはこちらから
資料ダウンロードはこちらから
Arvoで通勤管理を
今すぐ効率化